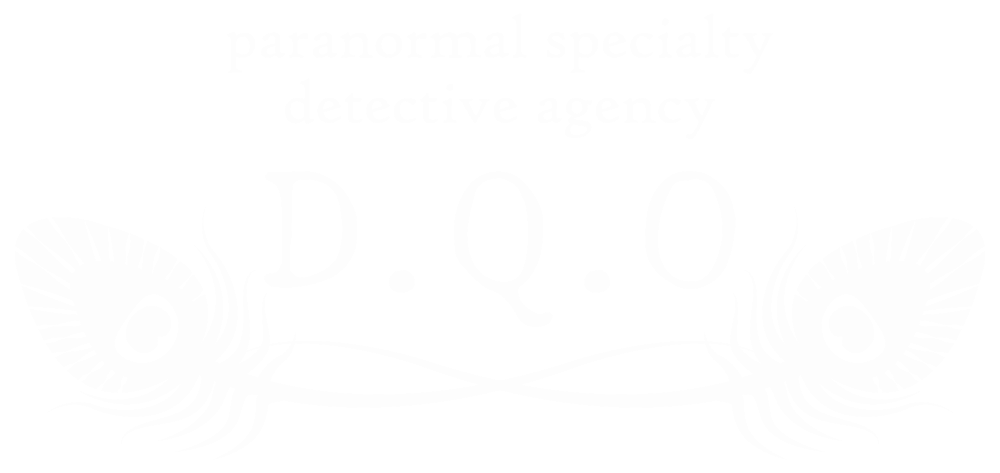プロローグ
「これは、この間飲み会で聞いた話なんだけどよ」
食後の気怠い時間帯。思わず零れる欠伸を噛み殺しながらレムナンが書類整理をしていると、よりダラけた声が雑談を振ってくる。
今この場には、僕ともう一人の同僚しかいない。そんな暇があるなら整理を手伝ってください、と普段なら小言を言いたくなるが……所長不在で空気が弛んでいるのか、この初春の陽気のせいだろうか、それを止めもせず目をやる。
仕事をサボっていてもどうやら叱られなさそうだとわかると、その男――沙明さんは、外の空気よりも暢気な様子で話の続きをしてくる。
「俺の研究室の先輩がよ、ちょっと前に引っ越しするっつーんでその手伝いしてたワケ。ソイツが礼代わりにつーんで飲みに行ってたんだけど、酒が回ったのか急に引っ越した理由を俺にべらべらべらべら喋ってきたんだよ。」
「……ちょっと待ってください、沙明さん。……そういう話、じゃないですよね」
昼間とはいえそういう話は、そういうモノを呼び寄せる。業務ならともかく、雑談で振る内容ではない。その説明は口が酸っぱくなるほどしている筈だが、まだ懲りていないのか。
低い声で話を遮った僕に対し、いやいやそんなつもりねーって、といつもの軽薄そうな笑みを浮かべたまま軽く否定する。
「その先輩が元々住んでた部屋って、相場の割に安めではあったが別に事故物件とも言われなかったし。なんつーか日当たり?そういうのが悪いからって説明されてたんだと。俺も何度か行って駄弁ってたけど、まじでなーんもないの。だから当たりの物件引いたっスね、なんて言ってんだよ」
なのに、だ。手元のスナック菓子をバリバリと食べながら話を進める
「卒業控えたこのタイミングで急に引っ越すなんて言うんだわ。なーんか臭ェとは思ったが、話を聞くと、最近になって部屋が真っ赤に染まる夢ばっか見るんだと。マジでそんだけ。な?気にし過ぎじゃねーの、とは思ったけどよ、『やっと卒業決まって最後のモラトリアムを楽しんでるのに夢見が悪いなんてたまったもんじゃない!』ってことで、早めに引っ越すことにしたってさ」
「それで?先輩さんは?」
「いや、それからなーんもナシ。4月から就職先の寮に入るから、それまで友達ん家を転々として毎晩パーリナイらしいぜ?夢見もすっかり良くなったって喜んでたよ。就職前のストレスだったんじゃねーかと俺ァ思うね…………労働ってやっぱ糞だわ、つー話よ」
食べ終わったらしいスナック菓子の空き箱をゴミ箱へヒョイと投げ入れると、これにて閉幕といわんばかりに手を一度叩く。
確かに話を聞く限り、ストレスによる一過性のものであった可能性が高そうだ。しかし頭ではそう理解しているのに、僕の直感はなにかが引っ掛かると小さく警鐘を鳴らしている。
「事故物件の告知義務は、ある程度時間が経てば……無くなります。だから、その先輩さんは、その期間が終わったあとに、そこを選んでしまったのでは……?」
「マジで?じゃあそういう物件だった可能性もあるっての?んー、でもそのソイツ大学生ん時からその部屋に住んでたんだぜ。足掛け6年近いのに今更ァ?って感じじゃね?」
「それは、確かに……そうですね……」
ヘラリと笑いつつ雑談を終えて気が済んだのか、沙明さんは自分のデスクへ戻る。そして頬杖をつきながら、パソコンを開き仕事を再開させる。その姿に内心溜息をこぼしていると、メッセージアプリらしい軽快な通知音が鳴る。
どうやらそれは沙明さんのスマホから鳴ったようだ。業務中だというのにマナーモードにすらしていなかったのか、じっとりと目線で訴える。今度こそ少し申し訳なさそうにしながら、沙明さんが片手でスマホを開くと「え」と、虚を疲れたような声を出す。
「何かあったんですか?」
「いや、さっきの先輩がさ……春休みが暇すぎて、部屋のジオラマ改造したから見てくれだってよ」
「仕事してください」
スマホの画面を見せてくる沙明さんの話を今度こそピシャリと中断させた。
静けさを取り戻した事務所内で自分の仕事に打ち込んでいると、ドアの向こうから石造りの階段を足早なリズムでカツカツと昇ってくる靴音が聞こえてきた。――この足音は……いつもより随分と機嫌が悪そうだ。
足音の主のためにコーヒーを淹れる準備をしておこう。そう席を立った瞬間、扉がいつもより強めに開けられる。青年というよりも少年といった方が正しい背丈に、パッと目を惹く端正な顔立ち。
しかしその顔に苛立ちを全く隠さない様子で、超常現象探偵事務所D.Q.Oの所長――ラキオさんが帰ってきた。
仕立ての良さそうなスプリングコートをハンガーにかけることなくソファーへ放り投げると、来客用のそこへドスンと腰掛ける。
「全く、わざわざこの僕を警察まで呼びつけたからにはなにか大した事件でもあったのかと期待したンだけどね。蓋を開けてみればただの失踪者事件とのことじゃないか。全く、自分達の無能さを晒すのは勝手だけれども、それに僕の貴重な時間を浪費させるだなンて一体何を考えているんだろうね。
いや、何も考えていないのかな?だとしたら頷けるね、理解はできるというだけで許せるという意味では勿論無いけれどね」
と矢継ぎ早に話し始める。なるほど、朝から不在にしたにも関わらず思ったような成果が得られなかったようで、それが彼のご機嫌を大層損ねている様子だ。
それにしても、うちの事務所はよく回る口を持つ人たちばかりだ。内心で僕は感嘆しながら、皺にならないようにコートをハンガーへ掛ける。
そして彼好みの温めのコーヒーをテーブルの上に置き、向かいへ腰掛けた。
「立て続けに同じマンションの同じ部屋で失踪者が出るというが、2人だけとのことじゃないか。そもそも期間もかなり空いている。
前回の失踪者が出てから10年以上経過して、次の住人がそこへ移り住んできたらしい。でもね、その2人目の住人も7年ほどその部屋へ住んでいたし、その間に管理者へトラブルの相談などもなかった。
ある日不意に消えてしまったとのことだが、その住人の関係者からは仕事でのストレスを溜めている様子があったとの証言も取れている。心霊現象を疑うよりも、その住人の受診歴などを調べてみるなど他にいくらでもやりようはあったンじゃないかと僕は思うんだけど?」
ここまで話すと、コーヒーを一気にあおる。そしてようやく一息ついた様子で、その白い眉間にきつく寄せられていた皺を少し緩めた。
あの堅物真面目を絵に描いたような、顔馴染みの刑事さん直々の依頼にしては確かに拍子抜けだ。その一連の失踪に、ラキオさんの興味をそそるような何かがあるようには僕にも思えなかった。
「部屋の写真も見せてもらったが、あれじゃ現状回復は難しいだろう、大家には気の毒なことだね」
「え?なにか、あったんですか?」
「ただ部屋が壁も床も天井も、そこに置かれた家財、ゴミ袋や玩具みたいなものまで全て赤い塗料で汚され、粉々に破壊されていたってだけだよ」
風呂場まで同様の有様だったらしいから、かなり精神に不調をきたしていたのかもしれないね。ウンザリとしたような口調に話す彼に対して、僕は沙明さんと顔を思わず見合わせる。
「なンなの?そうやって黙ってられると、気味が悪いんだけど」
「いや……その失踪に少し似た話を、ちょうど沙明さんから聞いたところでして……」
先程の聞いたばかりの研究室の先輩の話を軽く説明すると、ラキオさんも怪訝そうな顔を浮かべ、何かを思案するような仕草をみせる。
今の所、「赤い部屋」という共通のワードが出てきただけにすぎない。
怪談などで如何にもありがちなシチュエーションだ。
しかし先程、沙明さんから話を聞いた時に感じた、朧げな不安のようなものが明確な輪郭を持ちはじめている気がしてならなかった。
ジリリリリリリリリリリ
二人して顰めっ面をしていると、事務所の古めかしい電話がけたたましく鳴る。
静かに思索に耽ろうとしていたであろうラキオさんの目尻がピクリと動く。機嫌が再度悪くなる気配を察知したのか、沙明さんが珍しく機敏に受話器を取ると緊張感のない声で応対をし始める。
「ハイハイ、こちら超常現象探偵……って警察ゥ?さっきうちの所長様がお伺いしたばっかじゃねーの?要件はナニなわけ?
……アー……話の途中で勝手に……なるほど、そういうことっつーなら、もう一回連れてった方がいいかもしんないってーワケね」
ちょっと所長である僕に断りもなく!とムッとした顔でソファーから立ち上がるラキオさんに、電話を切った沙明さんがこう告げる。
「いつもの刑事サンから伝言だぜ、胡散臭い失踪は2件だけじゃない。頼むから力を貸してくれないか、だってよ」