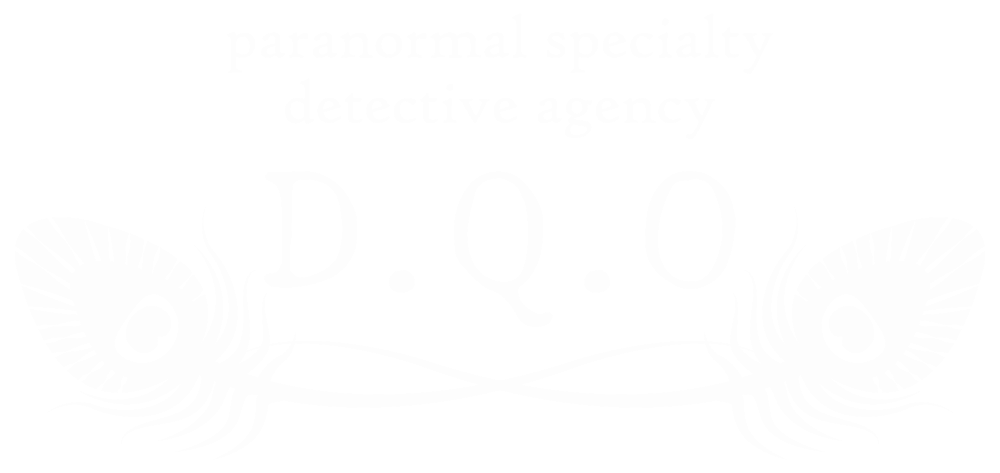序
思えば、私の人生はいつもその場凌ぎばかりだ。
なぜこんなところまで来てしまったのだろう。
私の目の前には今、磨りガラスがはめ込まれた木製の重厚な扉がある。
その扉の前でじっと立ち尽くしている、はたから見れば不審者以外の何者でもない陰気な女。それが私だ。
手帳に荒っぽく書き記されていた事務所の住所は、ここで間違いがない筈だが……。住所をスマホのマップアプリに入れた時、チラリと見えたここのレビューは黄色い星が一つ瞬いているだけだったことを不意に思い出す。
私の依頼なんて、まともに聞いてもらえるのだろうか。そもそも、話をしたところで、胡散臭い霊感商法などにあっけなく騙されたり、あれよあれよという間に怪しげな宗教に勧誘されたりするのではないだろうか……。一度不安が頭によぎると、とめどなくマイナスな考えばかりが浮かんでは消える。
――やっぱり、今からでも帰ろうかな。
ここまで来ておいて、どうしようもなく意気地なしの自分に乾いた笑いがこぼれる。逃げるように踵を返そうとした、その時だった
「そんなところにいつまでも突っ立ってられると迷惑なンだけど?この僕にアポイントメントを取り付けたからには、きちんと中に入ってきて説明する義務が君にはあると思うンだけどね」
まさか中から声をかけられるとは思っておらず、驚きのあまり小さな悲鳴が漏れる。扉越しにも関わらず、凛としていてよく通る声。その声に操られるかのように、冷たい金属製のドアノブを勢いよく回して中へ入った。
扉の先は、意外なほど明るい空間が広がっていた。
奥の壁一面は大きなガラスになっており、行き交う人々の様子が眼下に見てとれた。向かって左側には事務机が2セット置かれており、その奥は壁を覆い尽くすほど大きな書棚と膨大な本。右側には、入り口と同様に磨りガラスの篏められた扉が2枚ある。照明も椅子も、インテリア雑誌で見かけたことがあるものが置かれている。来客用らしいソファーも、私の買う家具メーカーではあまり見かけない細かな意匠が施されている。
全体的に歴史を感じさせる風情だが、煤けたとかボロボロという印象ではない。それらが嫌味なくこの空間にマッチしていて、高級なホテルのラウンジだといわれても納得ができる。
その光景に圧倒され、目線をあちらこちらへうろうろと走らせていると、小さな咳払いが聞こえた。そこでようやく、私は窓ガラスを背にゆったりと椅子に腰掛けている人物がいることに気付く。
そこにいたのは、青年というより少年といった風貌の子だった。逆光でハッキリと見えなくても、目鼻立ちが通っていて綺麗な顔立ちをしているのがわかる。年齢どころか、性別すら私の考えとは違うかもしれない。翡翠色の髪の毛が光に照らされて、キラキラ透けているのも相まって、まるでこの空間の調度品の一つのようだった。
この人が事務所のトップなのだろうか?あまりにも若すぎる。現実感のなさにそちらから目を離せずにいると、その人影がギュッと眉根を顰め、桜色の唇を開く。
「名乗りもせずに人の顔をジロジロ見つめて一体何なのかな?事務所の前で不気味に立ち尽くしているだけでなく、入ってきてまで不審者なンだ。全く、時間を浪費するのが趣味な輩がこれほどまでに多いとはね。ここに居を構えるまで僕は知らなかったよ。ああ、嘆かわしい。嘆かわしいね」
……今のは、彼が言ったのだろうか?ニッコリと微笑む天使のような姿からは、想像し得ないマシンガントークが飛び出す。驚きのあまり、魚のように私が口をパクパクとさせている間にも、彼の話は止まらない。
「君は仮にも依頼人じゃないのかい?それとも本当にただの不審者かな?もしくは、大層愉快な冷やかしだろうか?そんなものに付き合ってあげられるほど、この事務所も所長である僕も暇じゃないンだよね。おかえりならお早めに、どうぞ」
美しい顔に不釣り合いな苛立ちをたたえて、こちら――否、私の後ろの扉を指差しているようだった。そこでやっと我を取り戻し、慌てて自己紹介をする。
「あ、あの……すみません。依頼しました、坂東と申します。こちらで、不思議な事件について、調査されていると、お聞きしまして……」
土下座しかねない勢いで頭を下げると、頭ごしに大きい溜息がきこえた。そして掌をヒラヒラと振るとソファーをしめす。どうやら座れ、ということらしい。その態度に終始呆気に取られつつ、なんとか追い返されずに済んだことに安堵した。これ以上、彼の機嫌を損ねないように、可能な限り早く指示に従おう。腰かけたソファーは身体が沈み込むほどふかふかだったが、緊張を解けずにいる私は、石像のようにガチガチに固まっていた。
対する彼は、芝居がかった動作で窓際のオフィスチェアから立ち上がると、「お茶を」と誰かに内線をかけ、私の前のソファーへ座り直す。
「改めて、超常現象探偵事務所D.Q.Oへようこそ。僕がここの所長だ、さて前置きはいいから、本題に入ってもらおうか。手短にね」
「えっと……どこから話せばいいのか……」
「もちろん最初から。主観は不要だから、君はただ起きた事実のみを挙げていけばいい。不要か必要かは僕が取捨選択するからね。アハハっ」
こういう場での振る舞いがわからないので、一応尋ねてみたが一蹴されてしまう。何がおかしいのか分からないその様子に面食らいつつ、私はなるべく細かな情報まで、取りこぼしがないよう話していくことにした。
――1年ほど前から祖母の家で暮らすようになったんです。
ちょっと実生活で色々あって疲れてしまって……退職を機に少しゆっくりしようと思っていたところに祖母から『アキちゃん、帰っておいで』と声をかけてもらいました。祖母も随分高齢でしたし、新しい就職先を見つけるまで、介護しつつ甘えさせてもらうのもいいかなって。祖母の家は、なんというか……とても古くて、あっ、古いといってもこの事務所さんみたいなアンティークな感じじゃなくて、ただただ古めかしいというか……あっ、聞いてないですよね。すみません。
とにかく、そこでしばらく暮らしていたんです。祖母も高齢とはいえ頭はしっかりしていましたから、のんびり平和に暮らしていたと思います。でも、ひと月ほど前に亡くなってしまって。その死因自体には不審な点はないとのことだったんですけど……。
なんでしょう、初七日が終わった後くらいから……ですかね。家の中で物音がするんです。
さっきも言った通り古い家だし、一人になってしまったばかりなので気にしすぎかなとも思ったんですが……動物とか、風とかじゃないんです。ゾワっとするというか、気温が下がった気がするというか。それに、電話とかレンジが急に壊れたり、確かに閉めたはずなのに裏庭の鍵が空いてたり……とにかく、気味が悪くて。そんな時に、こちらの事務所さんの連絡先をたまたま見つけて……私、お坊さんとかそういう知り合いもいなかったので、なにか少しでも力になっていただけないかなって……すみません。
ここまで話し終えて、私はフーッと大きく息を吐く。
緊張のせいで、不必要なことまでペラペラと喋ってしまったかもしれない。合間に謝罪を差し込まずにいられないのも、話し終わった後に後悔するのも私の悪い癖だ。
気分を害されてはいないだろうかと、恐る恐る向かいの所長さんの顔色をそっと伺う。しかし彼は何かを思案するような仕草を見せているだけであり、どうやら私の要領を得ない話をきちんと最後まで聞いてくれていたようだ。ほっと胸を撫で下ろすと、視界の端からふいに手が伸びてくるのが目に入る。
「あの、お茶……どうぞ」
手の主は白髪の青年だった。音もなくヌッと現れた彼は、こちらをチラリと見ることもなくテーブルの上へ緑茶を置く。先程、所長さんが内線をかけていたのは彼だったのか。慌ててお礼を言おうとしたが、その人はそそくさと事務机の方へ戻っていった。所長さんよりは年上のように見えるが、それでも私より随分と年下のようだ。あと、目が全く合わなかった。もしかしたら私と似て……内気な性格なのかもしれない。そんな不躾なことを考えていると、所長さんが口を開く。
「話はおおよそ理解したよ。現時点では君のいう超常現象が発生していると明言できるような状態ではないけれどね」
「えっと、それは……私の家で起きていることは、お化けとか、そういう類のものではない、ということでしょうか……?」
思わず私はガックリと肩を落とす。やっぱり私の気にしすぎだと暗に言われたかのようで、顔にジワジワ血が集まるのを感じた。
「そうは言ってない。全く、凡愚なのはいいけれど人の話を最後まで聞くくらいの姿勢は見せて欲しいものだね」
「あの、つまり……?」
「超常現象であるという証明もできないし、そうでもないと現時点ではいえないというだけだよ」
フーと息を吐くと、所長さんは細い指を上へ向ける。そして何かのリズムを刻むかのように振りながら話を続けていく
「そもそも、だ。君たちは安易に『お化け』とかなんとかいうけれど、その定義は何だい?死人が枕元に立つ?祟る?ハッ、それらが現時点で科学的に立証できないものによって行われているという証明はどうやって行われた?データは?数値上の変化はあったのか?明確に物体が移動したという映像は?何もないだろう?それじゃあ困るンだよねえ、研究として客観的にそれらがあると証明することが僕の目的であり、この事務所の設立理由なンだから――」
次第に速度を上げて説明されていくせいで、半分も理解できない。ただただリズムに合わせて首を縦に動かしていると、今度は右奥の扉が開く音が聞こえた。
「ストーップ、所長サン?このオネーサン、話に全くついていけてないぜ」
扉の音ともに割って入ってきたのはまた別の黒髪の男性だ。「reference room」と書かれたガラス扉を後ろ手に大きな音を立てて閉めると、手にしていた薄いファイルを所長さんへヒョイっと投げるように手渡した。そしてこちらを上から下まで舐め回すように見たかと思うと、ニヤニヤと笑いながら軽く会釈してくる。……正直、苦手なタイプだ。前の二人とは随分違う。私は引き攣りそうになる頬をなんとか誤魔化しながら、会釈して返す。
所長さんは、話の腰を折られたことにやや不満げだったが、黒髪の男から受け取ったファイルを軽くパラパラと捲るとこちらをチラリと見る。そして顎でクイクイと白髪の青年を呼び寄せると、何かを耳打ちした。それに対し、白髪の青年はしばらく何かを考えるような仕草をした後、こちらを一瞥してフルフルと首を振っていた。
……なんだろう、すごく居心地が悪い。やっぱりこんなところへ来るべきではなかったのかもしれない。私はいつも判断を間違えてしまう。星1レビューの方が正しかったのかも……。所在なく手を組んだり解いたりしながら、カラカラに乾いた口でどうやって帰ると言い出そうかと考えあぐねる。しかし、所長さんの口から次に飛び出した言葉は意外なものだった。
「わかった、調査を引き受けよう」
「えっ、いい、んですか?」
まさか依頼を受けてもらえるとは思っていなかったので、ギョッとして思わず聞き返してしまう。
「二度は言わないよ。レムナン、この方に契約書を渡して」
レムナンと呼ばれた白髪の青年が事務机から書類を持ってくると、所長さんは手早く私にサインをさせ、満足そうに頷いた。
「あっはは、じゃあこれで契約成立ってワケだ。次は実際に住居を見させてもらうから、予定を空けておくンだよ」
あれやこれやという間にアポを取り付けさせられ、準備しておくものなどのリストを手渡される。そして所長さんは欠け一つなく美しいネイルに彩られた手を入口の方へ向けた。帰れという言外の意図を感じ取った私は荷物をまとめて、慌てて礼を述べながら入口から退散する。
階段を降りてから、私は小さく溜息をついた。
――新しい不安の種を、増やしてしまっただけかもしれないな。