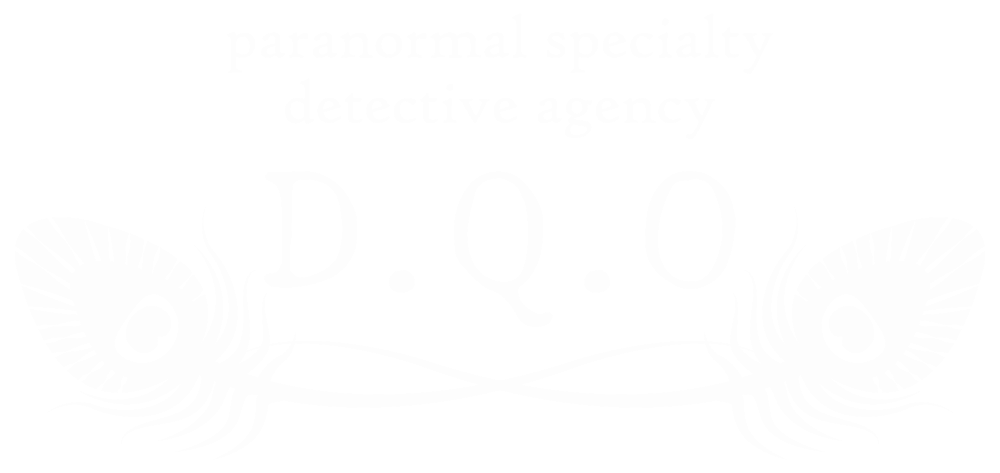翌朝。
いまだに気怠い身体を押して、事務所へ出勤する。
僕が扉を開くと、珍しく僕より早く来たらしい沙明さんがパソコンの前で固まっていた。
「なぁ、レムナン……昨日の写真、全部消えてるんだけど」
「え?」
SDカードは空っぽ。
慌てて自分のカバンからメモを取り出す。
しかし、そこでも僕の筆跡が途中で途切れていた。
まるで書いた瞬間に消されたように。
そこへラキオさんが入ってきた。
ツイードのジャケットを脱ぎながら、静かに言う。
「……あの家、なくなってたよ」
「取り壊されたんですか?」
「違う。最初から、なかった」
不機嫌そうに言うラキオさんに対し、僕らは顔を見合わせた。
「四十番地の三の隣は五。隣接している二軒の住居の間に存在出来る建物なんてい。……昨日のあれは、どこの記録にも残っていない」
沈黙。
部屋の時計の音が、やけに大きく響いた。
「……もしかして、俺ら全員で夢でも見たんじゃ」
「人間の脳が“異常”を忘れるようにできているって、言っただろう? もしかすると、僕たちの記憶も今まさにそうやって消されてるのかもしれないね」
「……やめろよそういうホラーなこというの!」
「ホラーもなにも、僕らが取り扱っているものはそういう類のモノだという認識だったけれど?」
つまらなさそうに溜息をついて、ラキオさんが続ける。
「欲を言えば、もう少し調査したかったけれど……データに残すことが出来ないンじゃ、僕の研究対象足り得ないな」
そう言って、彼は淡々と三つのカップに珈琲を注いだ。
湯気が立ち上り、周囲にインスタントにしては上出来の香ばしい香りが広がった。
「僕たち全員が記録できなかったなら、きっとそうしなければいけない何かだったンだろうね」
退屈そうに言うその声をどこか遠くに感じながら、僕は黙って珈琲を啜った。
その日の帰り道。
僕は無意識のうちに、昨日の通りに足を運んでしまっていた。
あんな事があったのに、どうしてここに。
……思い出してはいけないものを、思い出しかけている気がする。
早鐘を打つ心臓を無視して角を曲がる。
その瞬間、視界の端で何かが光った。
ほんの一瞬、白い壁の断片。
瞬きした瞬間には、もう何もなかった。
“人間の脳は、異常を忘れるようにできている”――。
ラキオさんの言葉が、耳の奥で反響する。
本当に忘れていいのだろうか。
それとも、忘れなければ――。
僕は深く息を吸い、何もなかったかのように歩き出した。
スマホのマップを開くと、そこには確かにあの家は存在しない。
四十番地の四は――存在しない。