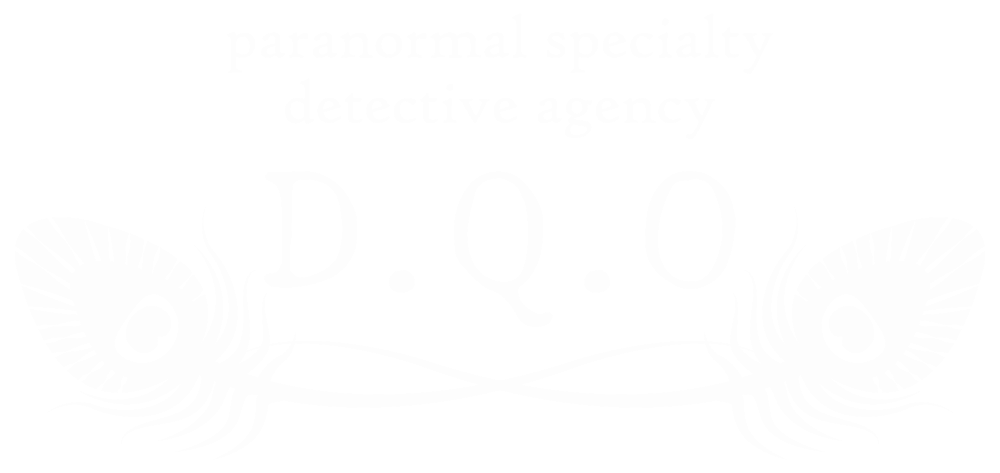夜十時。
僕たちは再びその家の前に立っていた。
静まり返った住宅街。風ひとつないのに、季節のわりには空気が冷えている。
時々チカチカと点滅を繰り返す街灯の下で、その家は昼よりも白く寒々しく見えた。
「……ほんとにやるんですか」
「ここまで来てその問答からまたやり直すつもり?調査だろう、ただの」
「ただの、ね……」
辺りを念入りに見回し、人がいないことを確認してから僕らはフェンスを越えた。
そして家の扉に手をかける。
――このまま、ドアノブが回りませんように。
僕の願いも虚しく、カチリと小さな音を立てて玄関の扉が開いた。
中は驚くほど綺麗だった。
持参した懐中電灯でそっと廊下を照らす。
新築の木の香り、玄関には砂埃ひとつ落ちていない、フローリングも誰も踏んだことがないように見える。
壁は真っ白で、家具も設置されていない。
「……なんか、懐かしいな」
沙明さんが小さい声で呟いた。
僕も、同じ感覚に襲われていた。
見たことがある。
来たことがある。
リビングの奥には階段、二階に行けば寝室がある――そんな確信が、頭の中にすでにあった。
「沙明さんも、ですか……?」 僕が言うと、ラキオさんは汚れひとつない白い壁を指でなぞる。
「人の記憶は自分の常識で空白を埋めようとする。記憶の再構築――積み重ねた知識や経験による演算ともいうべきかな。知らない筈のものを知っていると感じる、強烈なデジャビュ。だがしかしそれは、大抵は自分の中にある似た記憶を強引に当てはめて“理解した気”になろうとしているだけ。……何故そういう機能が必要か?それは、理解出来ないものへの恐怖を常に感じたままでは、マトモに生きていけないからさ」
――バタン。
振り返ると、玄関の扉が閉じていた。
風もないのに。
「風……ですよね?」
「そうだといいね」
沈黙。
廊下の奥から、何かの匂いが漂ってくる。焦げたような、濡れた土のような匂い。
不意にラキオさんは、ポケットから温度計を取り出した。
「ごらん。気温が五度下がってる。この季節に空調もないのにこの温度、間違いない。大当たりだよ、この家は」
目の奥に爛々と輝く喜びの光を湛えて言うラキオさんは、手にしたスマホのカメラで家の内観を撮っていく。
こうなってしまった所長は止まらない。
それを嫌と言うほど知っている僕は、なるべく早くここから出られるようにと現状についてメモを走らせていく。
この強烈な違和感。
どうしようもなく肌がピリつく感覚。
それを拭うように間取りの採寸をしようと、手持ちのメジャーを取り出そうとした。
その時だった。
ぽたり、
ぽたり。
どこかから不思議な音が聞こえる。
耳を澄ますと、それはどこかで水滴が落ちる音のようだった。
ぽたり、
ぼたり、
ぼた。
それが次第に速くなり、まるで何かの拍動のようなリズムを刻んでいる。
――ここは、危険だ。
二人に声をかけて、家を出ることを提案しようとする。
その時、ラキオさんが掲げたスマホのシャッターが廊下の奥を白く照らした。
その光の中に一瞬、男の影が見えてしまった。
ぼた、
ぼたた、
ぼたたたた。
耳の奥で、鼓動と異常な水音が重なる。
マズイ――
そう思った時にはすでに遅い。
ぐわりと天地がひっくり返り、視界がぐにゃりと歪んでいく。
「は?ちょっ、レムナン⁉︎」
慌てた声で沙明さんが僕を呼ぶ。
しかし、波打つ木目が眼下に迫る中――その声も徐々に遠くなり――遂には意識の糸がブツリと途絶えた。
目が覚めると、僕は事務所の来客用ソファーに転がっていた。
薄明かりの中で、天井の蛍光灯が滲む。
身体中が痛いのは、慣れない場所で寝たからだけだと思いたい。
「あ、起きた」
声のする方へ視線を向けると、沙明さんが向かい側のソファーに腰掛けているのが目に入った。
「すみません、あの……僕……」
「レムナンが現場で気絶するなんて随分久しぶりじゃね?随分長いことオネンネしてたけど、ちょっとはマシになったかよ」
軽い口調とは裏腹に、その夕日のような瞳には心配の色が見える。
僕は横たえられていた身体を気合いで起こすと、少しザラつく喉を開いた。
「ええ、もう……大丈夫です。あの後、何があったんですか?」
「いーや、何も?お前が急に白目剥いてぶっ倒れたから、慌ててタクシー呼んで帰ってきただけ。ラキオは一回自宅に戻るってたし」
そういうと、ほらよと言いながら机に置かれていたペットボトルのお茶を僕に投げて寄越す。
机の上に丸くついた結露の痕と、ぬるいそれが、購入してからどれだけの時間が経っていたのかを如実に表していた。
「入る時は、お前のお得意の“変な感じ”ってのはなかったのか?」
「ええ。なんとなく……沙明さんも言っていた、懐かしいような感じがしただけです」
「あー、アレなぁ。マジで意味不明な感じだったよな」
――行ったことないのに、なんか懐かしい友達ん家遊びに行ったみたいな。
そうこぼす沙明さんに、僕は黙って頷く。もっと言うなら、僕はあの家にずっと住んでいたような感覚さえ感じていた。
……そして、ここから出たくないとさえ。
ソレを自覚した瞬間、家全体がまるで一つの生き物のように何かを迎え入れようとしているのだと直感した。
気を失ってしまったのは、僥倖と言えるかもしれない。
あのまま、あそこに居たら……どうなっていたか想像もつかない。
カラカラに張り付く喉を潤そうと、貰ったペットボトルの蓋を捻って飲み干した。
「んじゃ、もう夜も明けそうだし帰ろうぜ」
そうあっけらかんと言う沙明さんに連れられ、僕たちは事務所を後にする。
とりあえず布団にはダイブしとけよーという声を背中に受けながら、それぞれの岐路についた。