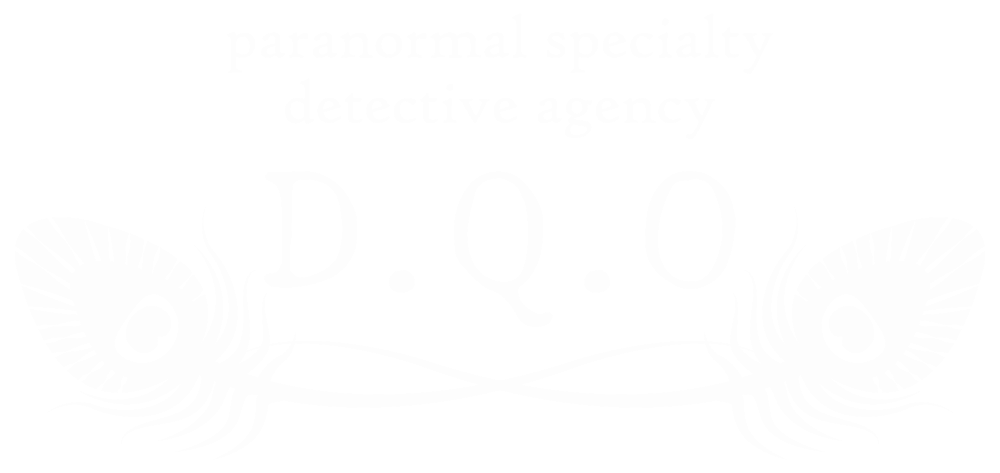事件は、数日後の夕方に起きた。
その日は依頼先が駅近だったため、珍しく三人で歩いて向かっていた。
結局、その依頼は一応ホンモノではあったものの、ラキオさんの興味を惹くようなものではなかったようだ。
拍子抜けするほど簡単にデータを集めた後は、知り合いのお祓い業者を案内して終わり。
想定より早く仕事が片付いた。
「思ったより早く終わったなー。飯行く?」
ウキウキとした気分を隠さないテンションで沙明さんが言う。正直心惹かれる提案だが、まだ勤務時間だ。
「……報告書をまとめてからにしましょう」
「まじめ〜」
沈みかけた陽の光が、街の角を朱く染めていた。
日が沈むたびに少し冷える季節。
人の気配が少ない住宅街を抜けようとした時、沙明さんが足を止めた。
「なぁ、ここ。こんなとこ、立派な家建ってたっけ?」
視線の先には、白いフェンスに囲まれた二階建ての新築住宅が建っていた。
新築だというのに、どことなく懐かしさを感じるのは、今どき珍しいサンルームがちらりと見えているからだろうか。
表札は掛けられていないが、施工会社のロゴと『分譲済』の札が掲げられている。
「……あれ?ここって、つい最近まで空き地じゃなかったですか?」
僕の記憶もあやふやだ。
毎日通っていた道なのに、そこに何があったか思い出せない。
「そうだったか?……いや、なんも覚えてねーわ。ここは我らが所長様に教えてもらおうぜ」
深々頭を下げて、変に芝居がかった仕草で恭しくラキオさんの方を指す。
しかし、ラキオさんは眉間に皺を寄せて黙ったままだ。
「ンー?ちょっと前にアレだけ俺に言ってたくせにィ、所長さんまっさかここが前なんだったか覚えてねーワケ?」
首を傾げながら、両手を口に当ててわざとらしくキャピッとぶりっ子ポーズをしている沙明さん。
それは清々しいまでに無視して、おもむろにラキオさんが胸ポケットからスマートフォンを取り出すと、見慣れたマップアプリを開く。
そして現在地と、今目の前に在る家をしばらく見比べると、一人で通りの角までスタスタ歩いて行く。
かと思うと一軒ずつ指差し数えながら、またここまで帰ってきた。
珍しく何も言わずに、不可解な行動をとるラキオさんを流石に奇妙に感じたのか、沙明さんが恐る恐る口を開く。
「エーット、ラキオ……さん?いや、あのちょっとした言葉のアヤみてえなもんだし……そんなに気にしなくても……」
「アハハ、気にしない?この僕が?いや、無理だね!」
沙明さんのビビりまくった声に対して、高笑いしながらラキオさんが返す。
その目は先ほどまでの仕事をしていた時よりずっと爛々と輝いており――それは同時に、僕にものすごく嫌な予感を去来させた。
「沙明。君って本当にこういうものから好かれないワリに、この手のものに気付くのがウマイよね!さすが我らが事務所が誇る釣り餌だね!エライエライ、褒めてるんだよ?」
思いもよらぬ言葉に、絶句する沙明さん。僕の方を見て、やっちまったと言わんばかりの目が僕と同じように嫌な予感に塗りつぶされていくのを僕は目ざとく察知した。
「えーっと、ラキオさん。あの……この手のモノ、っていうのはまさか」
「そうだよ、この家はね。存在しないはずの番地に建っているんだよ」
そういうと開いていたマップアプリをこちらへ見せる。確かにそこを見ると、この家の両隣はマップ上で隣接しており、この家が存在するスペースはないように見える。
「え?いやいや、んなわけねーじゃん。どっちかの家が古くなって取り壊してぇ、ちっさめの二軒に立て替えたとかじゃねーの?」
もっともな疑問だ。だがしかし、ラキオさんに違和感を指摘された途端、僕もこの家を見た瞬間におぼろげな違和感を感じたことを思い出す。――そう、デジャビュだ。僕は、この家を知る筈がないのに、どこかで見たことがある気がするのだ。
「そう、だからきちんと測定してきたよ。この土地のサイズはマップから計算するとやはり可怪しい。僕の歩幅で約十歩、つまり間口七〜八mもあるんだ。これはこの区画の他の住居の間口の距離の合算と、道幅が合わない。そう、この土地はマップ上明らかに異常なんだよ」
心底嬉しそうに語るラキオさんに対して、僕は背筋がぞわりと粟立つのを感じた。
「この家を見た瞬間、何か感じなかった?」
「……懐かしい、ような」
「そう、それが危ない。記憶は常に再構築される。脳は“知らない”ことを恐れるから、似た情報で補完して理解したつもりになる。――だから“見覚えがある”ように錯覚するんだよ」
ラキオさんの声が、興奮で少し震えていた。そして子供っぽく笑う。
「目の前に存在しているのに、論理的に存在し得ない住居。つまりこの家は、異界への境界線、ってわけさ」
「せっかくだから、調査していこうよ」
馴染みのカフェに入るような気軽さで、フェンスに手をかけてその家に入ろうとするラキオさん。
「いやいやいやいや!無断侵入はダメだって話、これ前にもしたよな!」
「そうですよ!僕たち、一応クリーンな商売でやっていこうって、この間誓ったばかりですよね⁉︎」
それを僕と沙明さんが必死に制止する。
「登記も住民登録もない家だよ。つまり所有者は“存在しない”ンだ。つまり、僕たちを裁ける法なんてないだろう?」
「いや、そんなの屁理屈だろ……!」
だが、ラキオさんはあっさりと言い捨てた。
「いいよ、じゃあ君たちはここで待ってれば。僕一人で――」
「行きます!行きますから!でも、せめて夜にしましょう!」
――夜になれば、人通りも少なくなる。ラキオさんが追い求めている存在たちにとっても、活動しやすい時間帯だ。
僕たちの説得を受けて――というより、様々なことを一瞬で天秤にかけたらしいラキオさんは「そう、じゃあまた二十二時にね」と唇をつり上げ言い残す。
そして、先ほどまでとは打って変わって軽やかな足取りへ事務所へ一人戻っていった。
その姿を見ながら、隣の沙明さんとどうか……今日の警察が怠慢でありますように……と祈るほかできなかった。