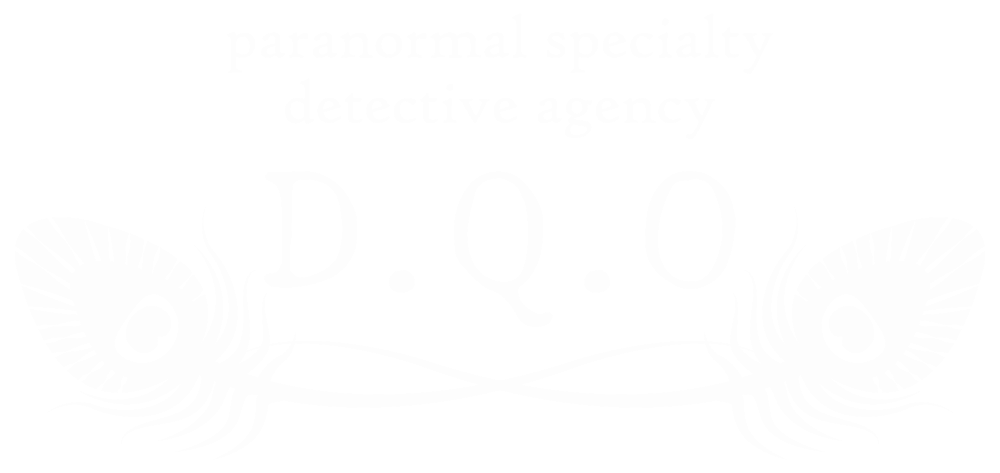「いっつも通ってるはずなのによ、取り壊されると何があったかって案外思い出せないもんだよな」
唐突にそんなことを言い出したのは、デリバリーのカレーを頬張っていた沙明さんだった。
スパイスの香りが満ちる昼下がりの事務所。午後からの予定は今日もなく、穏やかな空気が流れている。
向かい合わせた事務机の上に並べられているのは、出前で頼んだカレーとラッシー。それに加えて、「オマケだから。たくさん食べて」と微笑む店主のサービスで付いてきた、やたらと大きなナンが四枚。四枚も、である。
僕たちはそれをもそもそと食べながら、さすがにこのデカさのナン四枚は厳しいよな、なんてたわいもないことを話していた。その中でどう言う話の流れだったか、ふとそう言い始めたのだ。
「……確かに、ありますね。毎日通っているのに、ふと何があったか思い出せなくなること」
僕はスプーンを止め、少し考えてから相槌を打つ。確かにその状況には覚えがある。
毎日通っていたはずなのに、いつの間にか取り壊された建物、思い出せない看板。なんとなく気になって後からマップアプリで調べようか……と思ったことすら、目的地に着く頃には忘れているような、些細な日常の疑問。
「……そんなこと有り得る?毎日見ているものであれば、どれだけ興味がなくても、記憶に残って当然じゃない?」 チャイを片手に、キョトンとした顔で割って入ったのはラキオさんだ。
まるで坂道から転がしたボールがひとりでに手元に戻ってきた光景を見たかのような眼差しで、心底不思議そうにこちらを見ている。
「いや、まぁ、ラキオはそうかもしれねーけどさ〜」
その疑問が珍しく本当のハテナに満ちていたことを感じたのであろう。沙明さんは肩をすくめ、ナンを大きく千切って口に放り込んで続ける。
「んじゃよ、あのー、駅からいつものジャンクショップに向かう道あんだろ?そこの……アー、ちょっと行ったところにうどん屋あるじゃん。そこの隣だかなんだかって、今空き地になってんだけど何があったか覚えてっか?」
「正確に言うのであれば、うどん屋の北隣三軒目。そこは四ヶ月前まで本屋だったよ。しばらくシャッターが閉まっていただろう?個人経営の店に見えたし、おそらく店主が手放したンだよ」
ヒントすら曖昧で答えがあるかもわからない問題に、スラスラと答えるラキオさん。
沙明さんは「リアリィ?」とその細い眉を軽く上げる。
「えー、じゃあアレだ。いつもの警察署の近くに公園あんじゃん。あそこの角地、えらいデカい売り土地になってんなーと思ったんだけど。それもちゃんと覚えてんの?」「デカい角地ってまさか君、本当に覚えてないの?あそこは大学の分館があったじゃない。駅前に移転するから、取り壊しになったところだろう」
あんなに記憶に残る場所なのにどうして忘れられるンだいと、真剣にわからないといった顔でラキオさんは言っていたが、僕も正直何があったか覚えてなかった。
「うーわ、マジかよ。やっぱ俺らの所長の灰色の脳みそは凄いわ。マジ尊敬するわ」「その微妙にズレた点を僕は親切だから訂正してあげるけど、それをいうなら『灰色の脳細胞』だからね。小学生でも知っているよ、全く」
一通りクイズをしあった後、大きく演技がかった態度で溜息をつくラキオさん。その仕草は相変わらず、あらゆる方向に敵を作るタイプのものだ。
「まぁ、人間の脳は不必要だと判断したモノ、興味のない情報を積極的に“捨てる”ように出来ている。選択的忘却くらいは聞いたことがあるだろう?つまり、君たちは無意識のうちに、記憶を削除してしまっているのさ。それが本当は必要なものかもしれないのに、機械的に、事務的に――ね。だからそのお粗末な記憶力とやらも、人間らしさの証拠なンじゃない?僕には全くもって理解出来ないけどね」
「ラキオさん、そういうこと言うと……本当に嫌われますよ」
「どうして?忘れられるってことは、人間としての防御機能が正常に働いているって教えてあげてるだけだろう。その代わりに、現実を一枚削っているだけさ」
尚も止まらない楽しげな講義を聞きながら、僕は思う。 普段は物をあまり好んで摂取しないラキオさんが、僕らがカレーを注文するときにだけ「チャイも頼んでおいて」と言うのを。
そして、それを食事を摂る僕らが見える場所でわざわざゆっくり飲んでいることも。
こういうかわいげが、もっと多くの人に伝わればいいのに。
そうすれば、マップアプリの星の数も増えそうなものなのに――と。
最後のナンの欠片を咀嚼し、僕は静かに息をついた。