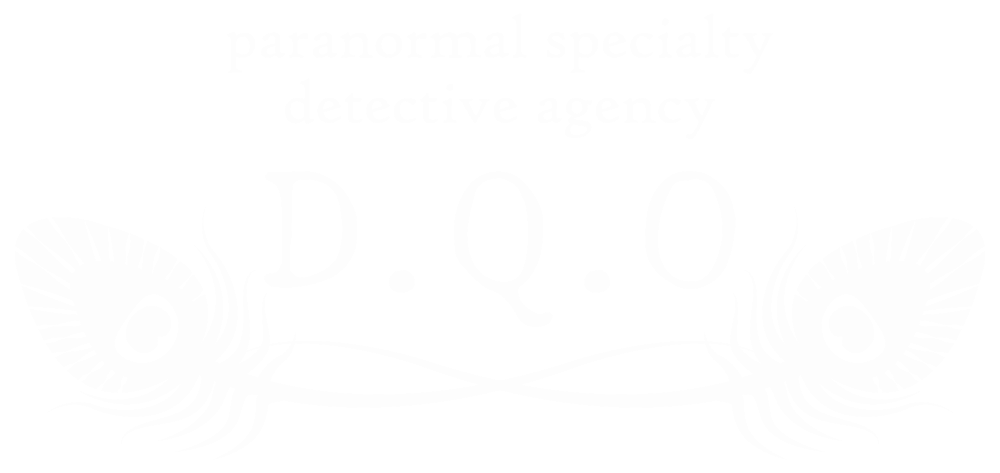レムナンが探偵事務所から帰る頃には、日はすっかり傾いていた。帰りに軽くコンビニで買い物も済ませたので、身体はじっとりと汗ばんでいる。重い荷物を片手にまとめて、慣れた手つきで数字のタグしかつけていない飾り気のない家の鍵を取り出す。ドアノブを回し部屋に足を踏み入れた瞬間、妙な気配を感じた。8月に近いというのにいやに空気が冷たい。震える手で廊下の電気をつけると、冷気の原因は否応なしに視界に入ってきた。……冷凍庫の扉が少し開いている。
――しまった、閉め忘れたんだ!
あの事務所に相談へ行ってみようと決めていたものだから、朝から気もそぞろになっていたに違いない。前の工場の仕事を辞めてから、しがないバイト暮らしである今のレムナンに冷凍庫の食材全滅はなかなかに金銭面で厳しいものがある。レムナンが慌てて冷凍庫の中身を確認すると、中に入れていた肉やアイスなどはカチコチとしっかり凍ったままのようだった。
ほっと息をつき冷凍庫の扉を閉めると、今度は買ってきたものを手早く冷蔵庫へ入れていく。ゼリーや栄養ドリンクなどしかないが、あの事務所に行く前と比べると少しは食欲が出てきている自分に気付く。そうだ、さっき冷凍庫に見えたアイスも食べてしまおうなんて、珍しく少し浮ついた気持ちで冷凍庫の扉を開けようとした時、ふとレムナンは気付く
冷凍庫の扉を閉め忘れた?
だとすればそれは、いつから?
レムナンは朝一番にあの事務所へ相談に出かけたきり、一度も帰ってきていなかった。朝に閉め忘れたのであれば、中の食品が溶けていないなんておかしいじゃないか。帰宅した時とは違う嫌な汗がじわりと身体から噴き出すのを感じる、地面がグニャリと歪んだようでその場に目を閉じて蹲った。
気のせい、気のせいだ……
最近嫌なことばかり起きるから、過敏になっているだけだ。相談した件だって、思えば昔に視えていたあの女の霊に比べれば可愛いものだ。冷凍庫は少し隙間が開いていただけだったのかもしれない、だから中身は無事だった。たったそれだけのことじゃないか、運が良かった。そう思えば大したことはない。今日会った超常現象調査の胡散臭い探偵だか霊能者だかだって
「なんでもかんでも霊に結びつけたがるような奴は一定層いるけどね、幽霊の正体見たりなんとやらと言うだろう。そう思いこむと人間の脳なんて単純なモノだからそう感じてしまうだけにすぎないことが圧倒的に多いんだよ。論理立てて考えれば説明できない事柄なんて、この世に滅多にあるもンじゃない」
と言っていた。あまりにも横柄な態度にくるくると回る口、これでよく仮にも客商売が務まるものだと面食らったが、まとまりのないレムナンの話を遮ることなく最後まで聞いてくれた変わった人。予約もなしに飛び込んだから嫌味もたっぷり言われたような気がするが、常に真っ直ぐ前を見据えているあのピーコックグリーンの瞳、自分にはない自信に満ち溢れたあの態度を思い出すと、不思議と少し心が軽くなる気さえした。マイナスの方へよく働く自分らしい思考を堰き止め、深く息を吸っては吐く。枯れ尾花で身体まで病んでしまっては元も子もないので、無理にでも楽しいことだけ考えるようと努める。そういえばあの人には明日また事務所へ来いと言われていたな、少しでも食べて休まなければ……
――アイスはやめて、買ってきたゼリーでも食べようかな。それで積んでいたゲームでもして、それで………
と硬く閉じていた瞳をゆるゆる開いた。
瞬間、視界の端にキラリと輝く金色の糸。蛍光灯に照らされ、美しく輝くそれはどこからきているのか、視線が吸い寄せられるようにその先を追っていってしまう。身体と心がほつれているようだ。心はやめろと叫んでいるのに、頭がぼうっとしてうまく指示が入らない。
「……あ……」
閉めたはずの冷凍庫の扉の隙間からそれは垂れ下がってきていた。扉はゆっくりとこちらに向かって、なおも開いてきているようで……そして……
弾けるように立ち上がり、着の身着のまま飛び出した。少女のような愉しげな嗤い声が追いかけてくる気がして、言うことを聞かない足を懸命に動かす。出ていく時に冷凍庫の隙間から見えてしまった、あの無機質な瞳が脳裏にこびり付いて離れない、確かに捨てたはずなのに、どうして、どうして……。込み上げてくる胃酸を胸を殴って無理矢理おさめ、ふらつく身体とまとまらない思考のままあてもなく街を彷徨う。もう家に帰る気にはなれなかった。