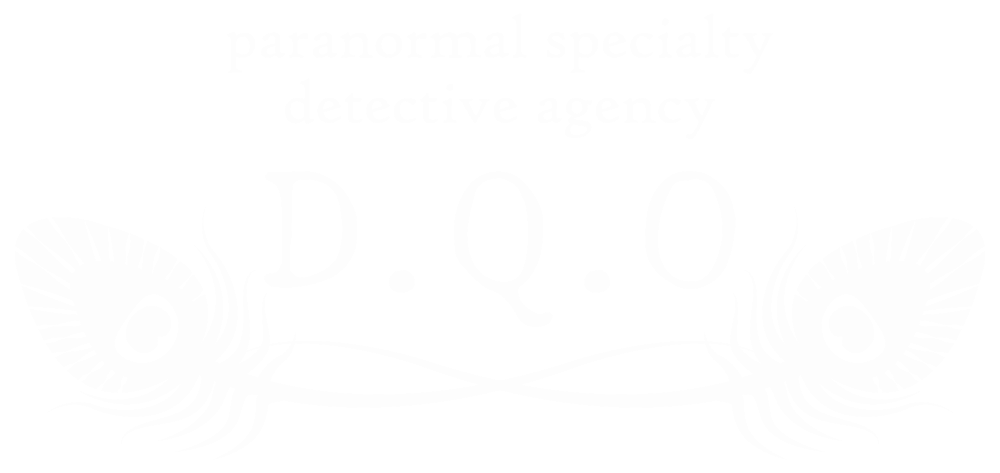結
「あは、ははは……なんだ、最初から全部わかってらっしゃったんですか?私がアキちゃんじゃないって」
身体から力が抜ける。
笑える。笑ってしまう。乾いた笑い声が、部屋の壁にぶつかって空虚に跳ね返った。
所長さんも、沙明さんも、レムナン君も、誰一人として口を開かない。
沈黙が、鋭い刃物のように横たわっていた。
「坂東アキ、はもういません」
私は目を伏せ、ゆっくりと笑う。
「私の本当の名前は……所長さんはもう調べ上げてくださってるのかもしれませんけど、もう関係ないでしょう?」
所長さんの瞳が、スッと細められる。
――怪異の調査をしているときは、あんなにキラキラとビー玉のように輝いていたのに。今は氷のように冷たく、どこか愚か者を憐れむような光を湛えていた。
「何故、成り替わりなんて真似を?」
彼が凛とした低い声で問いかけてくる。
その声には、怒りも嘲りもない。ただ、真実を知りたいという誠実な静けさだけがあった。
「”何故“?そんなの、簡単な話です」
天井の古い蛍光灯が、ブンと低く唸る。
外では風が、ひゅうと鳴いていた。
まるで誰かが、この話を聞くのを嫌がっているかのように。
「アキちゃんはね、綺麗なんです。
頭も良くて、顔も良くて、皆に愛されていた。アキちゃんの一言で、彼女の周りの世界は簡単に動く。――神様なんですよ」
言葉が漏れるたび、胸が高揚でじんわりと熱くなっていく。
「中学の頃、彼女に虐められました。ただ席が近かった、それだけの理由。……でもね、怖いより先に“美しい”って思った。私を安い玩具みたいに踏み躙る彼女は、キラキラと輝いていました。彼女だけが、この世界で自由なんだと思いました」
私は頬を撫で、うっとりと目を閉じる。
廊下がキィキィ鳴った気がしたが、誰も動いてはいない。
「高校でも、大学でも、追いかけました。一等輝く私のお星様。もう私のことなんて、捨てた紙クズよりも記憶に残ってなかったでしょうけど、それでも良かった。遠くで見ているだけで満足でした……でもね」
私は喉の奥で笑った。
「婚約したって聞いたんですよ。“普通”の女になってしまうなんて。誰かのものになるなんて――つまらない。神様は神様のままでいてくれないと」
声が熱で上ずる。喉の奥から笑いが込み上げた。
「だから――私が、永遠にしてあげたんです」
誰も息をしていないようだった。
沙明さんの拳が、真っ白く握られているのが見える。
「……殺したのか」
掠れた声で、やっと彼が尋ねてきた。
「違いますよ」
私は大きな声で笑う。
「彼女がアキちゃんでなくなっただけ。だから、私が代わりに“アキちゃん”を続けてあげたんです。救ったんですよ、この世界のために」
畏れ多くも仕方なくですよ、と私は困った顔で首を振る。
誰かが「狂ってる」と呟いた気がしたが、私には関係のないことだ。
「幸い、体格は似てましたから。少し弄るだけで案外簡単にアキちゃんになれましたよ。当然ですよね、私は誰よりもアキちゃんの理解者なんですから」
レムナン君が、耐えきれないように私から目を逸らした。
その瞳の奥に、言葉にできない何かを見た気がする。
「……これってなにか問題になりますか?せいぜい、おばあちゃんの遺産を不正受給しているとか、保険のアレコレとか……それだけ。私は愛するアキちゃんを演じているだけです」
そう、たったそれだけだ。
愛する存在が世界から失われそうになった。だからそれを繋いでいる。こんなにも簡単なこと。
「所長さんたちだって、別にアキちゃんの“行方”を知りたいとか、そういうわけじゃないんでしょう?……正義のために働くとか、そういうタイプでもありませんよね?きっと」
私が三人の方へ微笑みかける。
けれど三人の瞳は、氷のように静まり返っていた。
そこにはただ、人の形をした何かを見つめる観察者の冷たい光だけが残されていた。
ああ、アキちゃんなら上手くやれたのに。やっぱり私は、出来損ないだ。
フゥ……と自嘲気味に息を吐いて続ける。
「でもね――私が一人になってから、時々おかしなことが起きるようになりました」
風もないのに、天井からパラリと埃が舞い落ちた。
日が落ちてきたのか、部屋の空気が徐々に冷えていく。
「そうしたら不安になったんです。私、ちゃんとアキちゃんを救えていなかったのかもって。だから、確かめたかったんです」
その言葉に沙明さんが、低く呟いた。
「……それが、俺たちを呼んだ理由か?」
「ええ」
私は柔らかく笑みを浮かべる。
「あなたたちなら、“この家にアキちゃんがいる”って証明してくれると思って。それが、何を伝えたいのかも――」
――結果としては、そこまで望めなかったわけだが。
胸に去来する落胆を、私は溜息と共に吐き出した。
その音に気付いたのか、レムナン君が徐に顔を上げる。
その瞳には、暗い炎のようなものが揺れていた。
「……何を伝えたいか、ですか?教えてあげますよ、ここにいる何かが……ずっと、僕に言ってきたことは――」
ずっと堰き止めていたものが決壊したかのように、彼は続きを口にしようとした。しかし、その言葉を所長さんが遮った。「もういいよ、レムナン。時間の無駄だ。僕の疑問は解消できた。これ以上の長居は不要だよ」
そういうと、机に並べられていた資料を無造作に彼は閉じる。
「でも……ここにはまだ、本物のアキさんが――」
「アキ?やっぱりそうなんですか?レムナン君に見えている長い髪の女性って、本当に、本当にそうだったんですね!」
尚も言い募ろうとしたレムナン君の言葉に、思わず声が弾んだ。
「やっぱり……いたんだ、アキちゃん。ずっとここに……!」
胸が高鳴る。心臓が痛いくらいに脈打つ。
「嬉しいな……ずっとこうしていたかったの。嬉しい……嬉しい……!」
笑い声がこぼれた。軽やかで、どこか幼い。
花びらが風に舞うように、私はその場で小さくくるりと回った。多幸感で胸が詰まり、視界が滲む。もう、そこにいる他人のことなど、どうでも良かった。
その様子を見ながら、所長さんが冷たく言う。
「最初に言っただろう?もし|本《・》|格《・》|的《・》|な《・》|除《・》|霊《・》が必要になったら、必要な人間を寄越すと。それまでは――幸福な世界で生きてればいいンじゃない?ここにいる“何か”と一緒に、くだらない愛とやらに溺れてさ。依頼は、ここで起きたことの解明だけ。それはすでに終了している。これ以上は僕の知ったことじゃないね」
彼は一瞥すらくれず、私に背を向けた。
「さようなら。せいぜい、良い夢を」
風もないのに、カーテンがふわりと揺れた。
透ける白布が闇の中でゆらめき、まるで見えない誰かが踊っているようにも、逃げ惑っているようにも見える。
私は思わず手を伸ばした。そこに、確かに温もりがあった気がした。
「アキちゃん、ねえ……もう行かないで。ずっと一緒にいようね」
静かな部屋に、私の声だけが響く。
遠くで、サイレンの音がゆっくりと近づいてくる。
けれど私には、それが何の音なのか、もう分からなかった。
ただ小さく笑いながら、私は踊り続けた。
見えない誰かと、永遠に。