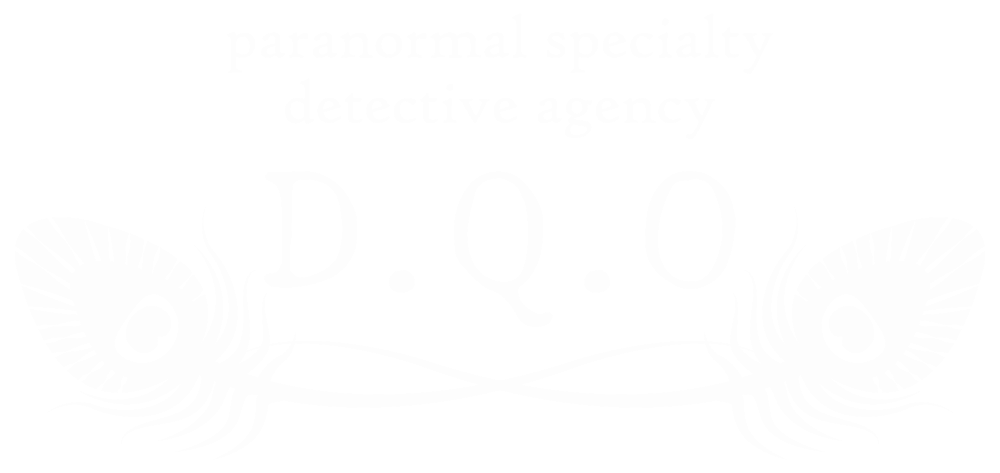八
鼻歌を歌いながら私は台所に立っていた。
あの事件から数週間。あれほど人々の頭を悩ませていた苛烈な日差しはすっかり翳り、代わりに柔らかな風が窓を揺らす季節になっていた。
調査をお願いする前までは、夜な夜な響く家鳴りや、勝手に動く食器が気味悪くて仕方なかった。けれど今では――レムナン君には見えていたという“霊”の仕業かもしれないと思うと、どこか愛おしい。
お婆ちゃんが亡くなってから、この家に私ひとりきり。あの時私は初めて、「寂しい」という感情を知った気がする。ここに来るまではそんなことを感じたこともなかったのに。随分贅沢になったものだと、自重気味に笑ってしまう。
少しヒビの入った窓を開けると、どこからか花の香りを含んだ風がふわりと吹き込んでくる。その香りを胸いっぱいに吸い込んで、すっかり気持ちのいい気候になったなと私は目を閉じる。
ガス釜で炊いたお米の香りは今日も素敵だし、常備菜は何品か残っている。冷凍のお肉は先日使い切ってしまったから、今日は旬で安くなっていた秋刀魚をグリルで焼いて合わせようか。徐々に色がついていき、ジュウジュウと皮が弾ける音を想像するだけで、お腹の底がくすぐったくなる。脂の乗ったでっぷりとした秋刀魚に塩を振ってから、待ち時間で炊き立てのご飯をよそう。まずはおばあちゃんたちのお仏壇へお供えをして……と楽しく準備をしているところに、ピンポーンと軽快な音が鳴った。
なにか宅配を頼んでいただろうか?
仏壇の蝋燭の火を消し、玄関へ向かう。引き戸を開けると、先日までお世話になった所長さんたちがそこには立っていた。
「あれ?所長さんたち……?この度はお世話になりました、えっとお忘れ物とか……?」
急に彼らが訪問してくる理由がわからず、なんとなく思いついたことをそのまま聞いてみる。どれも高額そうな機材だったから、ケーブル1本でも残っていたら事だろう。掃除している時には見かけなかった気がするが、どこか隙間にでも入り込んでしまっていたのかもしれない。しかし、所長さんからの返答は予想だにしないものだった。
「少し気になることが残っているンだよね。依頼は終了したけれど、ちょっと話をさせてもらえない?」
「ええ、それは構いませんが……」
恩人たちのお願いを断る理由などなかった。とりあえず先日まで彼らが使っていた部屋へ案内する。自分以外の足音が久しぶりにこの家にキィキィと響いた。
部屋に入っても、三人は腰を下ろさない。立ったまま、静かに私を見ている。お茶でも、と言いかけたが所長さんの手がそれを遮った。
半月ぶりに見る彼らの顔。沙明さんもレムナン君も、どこか顔に少し疲れの色が見える。前と変わらないのは所長さんくらいのものだ。ここにいる4人の中で一番小柄なはずなのに、たっぷりとフリルが襟にあしらわれたブラウスに身を通し、誰よりも華やかな存在感で堂々した立ち姿は舞台俳優のようだ。
「えっと、それで……お話というのは?」
沈黙に耐えかねて、私が口を開く。すると所長さんは艶やかな笑みを浮かべながら、真っ直ぐ指をこちらに向けた。
「聞きたいことがあるのさ。――坂東アキ、君本人にね」
「……私に、ですか?」
「ああ、そうさ。そもそもなぜ僕がこの依頼を受けたか、話してあげようか」
「それは……私の依頼が、所長さんの期待するような……案件だと予想されたからではないんですか?」
「まぁ、蓋を開ければそうだったけどね。僕の興味を最初に惹いたのは、案件じゃない。そう君自身だよ」
思いもよらない言葉に、私は息を呑む。所長さんの声が静かに続いた。
「坂東アキ。君は以前にも僕の事務所に相談を持ちかけているね。メールフォームすら通さず、いきなり電話口に自分の都合を捲し立ててきた。随分と尊大な依頼人だと思ったものさ」
カラカラと笑いながらも、その青い瞳に無邪気そうな色は見られない。
「そして結局、電話口で僕と数度話しただけで随分と鼻息荒く……僕たちのことを馬鹿にした暴言を吐いて切ったンだ。印象的な態度だったから、しっかり記憶に残っていてね。そんな人物が一年後、殊勝にも再び依頼してきた。……さて、一体どういう風の吹き回しかと興味が湧いた」
思わず私は唇を噛む。心臓がドクン、とゆっくり音を立てた。「そ、んなことも……ありましたかね、すみません。あまり、覚えていなくて……あの、少しメンタルが乱れていた時にかけていたのかもしれません。その節は、ご迷惑をおかけしました」
「フン、君に謝罪されても無意味だよ。――電話越しに話した君と、実際に会ってみた君――まるで別人だったよ。何があったものかと考えあぐねたものさ。霊障に悩むうちに精神を病んだのか、あるいは“憑かれた”のか。それを確かめたくて、僕は並行して調べていたのさ。そう、君自身のことを」
そういうとレムナン君が背負っていた大きなリュックから、大きなファイルを取り出した。黙ったままそれを机の上に広げていく。そこには私の経歴、診療記録、過去の写真――どう考えても真っ当な手段で手に入る情報ではないものが並んでいる。
「勝手に、そんなことを……」
「アー……、ホント勝手にこんなこと調べてすみません。でもウチの所長は気になったことは突き止めるまで止まんねえもんで」
沙明さんが心底申し訳なさそうな声を出しつつ、ページをパラパラ捲る。その手がある1ページで止まった。
「これを見ると、貴女の経歴の華々しさにビックリしたっつーか。俺でも知ってるような大学にストレート入学、友人も多く、ミスコンにも出てらっしゃるみたいで。これはお知り合いからの情報ですが、綿密なお付き合いをされていた男性も多かったらしいっスね」
その中でも――と彼の指が一枚の写真を指差す。それは、見覚えのある男の顔。
「その中でもコイツは有望株」
その写真を一枚ピッと取り出すと、私の方へ向ける。
「この男の名前、わかるか?」
「……」
唇を噛みながら、蛍光灯に照らされたそれを私は無言で睨みつける。それは先日、ここでレムナンくんに取り押さえられ、警察に連れて行かれた“あの男”と同じ顔だった。
「わからないはずないよねぇ?どれだけ君が薄情であったとしても――仮にも結婚するかの瀬戸際だった相手だよ。」
「……嫌な記憶は、積極的に忘れるようにしているもので」
「それだけでは、ありませんよ」
首を振る私に、レムナンくんが言う。そして彼は手袋をつけたまま、ジッパー袋に入れられた古びた日記帳のようなものを取り出した。
黄ばんだページの隙間から、ボールペンのインクが滲んだ筆跡が覗く。
「これは、坂東アキの祖母のものです。先日少し……お借りしました。随分と、几帳面な方だった……みたいですね。そこに、気になる内容がありました」
――
アキが1年前に急に帰ってきた。
昔は私たちにも高圧的な孫娘で、最後にきた時は親に無理やり連れられてきた学生の時だったか。
その時すら、ずっとスマホで友人らしい存在と電話をしていた。親がいなくなると、私たちから『お小遣い』と称して、幾らか金銭を捲き上げてどこかへ消えた。
そんな孫が急に帰ってきたものだから――てっきり今までの何かで因果応報な目にあったか――碌でもない理由で私の元へ来たのだろうと身構えた。
でも、戻ってきた「アキちゃん」は優しくていい子だった。
ずぶ濡れで大きな荷物を持ったまま、「おばあちゃんしか頼れる人がいない、助けてくれませんか」と玄関先で蹲る彼女。その姿を見て、私は黙って家に受け入れた。
「アキちゃん」は仕事を辞めて、婚約者からも逃げてここにきたのだという。私にも一応結婚式の招待状は来ていたというのに。そこから一体何があったのか。
私は何も聞かなかった。聞こうとも思わなかった。だってあまりにもいい子だったから。
私のご飯を食べて、私の世話を甲斐甲斐しくしてくれるその子は――最初はビクビクとしていたものの、徐々に心を開いてくれたようだ。
理想の孫娘との穏やかな日々。それは伴侶を失ったばかりの私にとって、幸せなものだった。たとえそれが、違和感全てを無視したとしても。
この子は一体誰なのか。誰でもいい、この子が「アキ」ならそれでいい。
――
読み上げられる文字は、まるで呪文のように部屋の空気を変えていった。紙の擦れる音だけが、時計の針のように静かに響く。
私は笑って誤魔化そうとしたが、喉が渇いてうまく声が出なかった。
「……おばあちゃんは、年相応の物忘れがありました。だから、記憶が……混乱していたのかもしれませんよ」
「かもね。けど、ここでもう一つ面白いものがあるよ」
所長さんが一枚の写真をテーブルの上に置いた。
そこには、沢山の人間に囲まれたアキと――少し距離を置いて映る、冴えない一人の“女”。
私の視線がその一点に吸い寄せられた。
指先がかすかに震える。
白い光に焼かれた写真の中で、女は笑っていた。けれどその笑みは、どこか私の顔に似ていた。
――いや、似ているのではない。
その瞬間、天井の蛍光灯がわずかにチリと鳴り、光が揺れた。
沈黙の中で、誰もが同じ結論に辿り着いていた。
所長さんが静かに口を開く。
「では、今ここにいる“坂東アキ”……キミは一体、誰なのかな?」