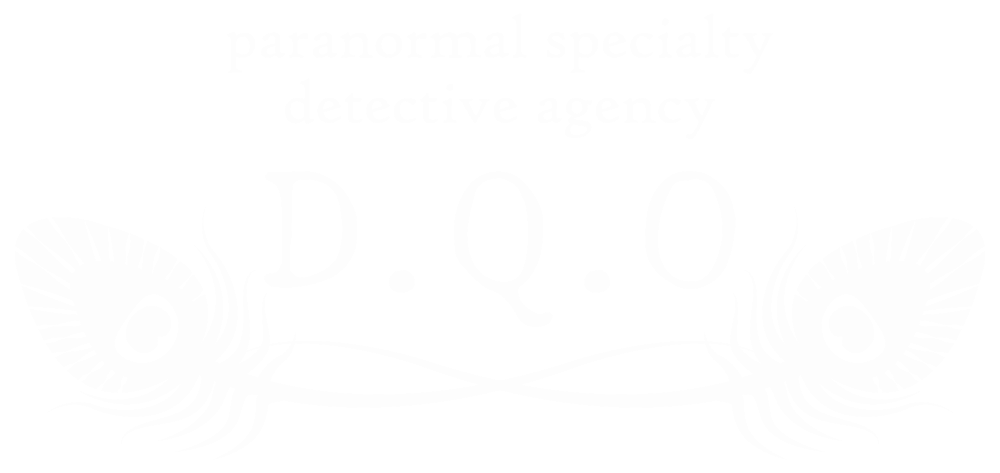六
まだ微睡む身体に、嫌に騒々しい言い争いのような声が耳に入る。
重たい瞼を必死に上げると、レムナンとラキオがなにやら向かい合って言い合っている。ぼんやりとした頭で手を伸ばし、枕元を探るとやっとメガネに触れた。かけると視界がハッキリして、ラキオの眉根がきつく寄っているのが見えた。
「沙明、随分とお早いお目覚めじゃないか。早速だけど――緊急事態だよ」
「……撮影していたデータが一式、まるごと消えているんです」
「な……」
嫌な予感が的中した。俺は陸に打ち上げられた小魚みたいに口をパクパクさせてしまう。
レムナンは一睡もしていないのだろうか。困り果てたように頭を振る彼のクマはいつもより一層酷い。
「霊障によって、機材にトラブルが生じるという例は多々あります。今回も、裏庭の件とは別口で……この家にいた何かの干渉によってデータが一時的にバグを起こしているだけの可能性もあります」
「というわけで、あの裏庭の侵入者を指し示す物的証拠は僕たちの手からすり抜けてしまったというわけさ。これから映像の復元をするために、僕とレムナンは一度事務所へ戻るよ。君は……そうだな、不法侵入の現場に立ち会ったわけだし、物証はないが、いつもの刑事なら邪険にされることはないだろうからね。相談したという実績を残しておくためにも、一度依頼人を連れて警察へ被害届を出してくれ」
つらつらと話しながらこちらに視線を向けもせず、ラキオは荷物をテキパキとまとめていく。霊が映像を消したなんて、普段のラキオであれば大喜びしそうなモノだが、その表情は珍しく苛立っているように見える。その矢継ぎ早の指示に、聞き漏らさないよう相槌を打っていると、やがてラキオは俺の方をちらりと向き、孔雀色に彩られた指先をこちらへまっすぐ向けてこう言った。
「……依頼人を必ず見ておくように。何かあればこちらから連絡をするから、すぐに確認できるようにだけしておいてね」
ラキオの淡々とした命令に、俺は黙って深く頷く。
俺たちの乗ってきた車で警察署へ向かうように伝えられた俺は、すぐさま依頼人サンに事情を説明した。
一連の話を聞いて、依頼人サンは可哀想なくらい顔が真っ青になっていたがコクコクと首を縦に振ると、すぐに出かけ支度を始める。戸締りはしておくから早く行きなよと言うラキオとレムナンに家の鍵を預け、怯えた様子の彼女が車に乗り込んできた。助手席のシートベルトが締めるのを確認し、俺は車を発進させた。
警察署へ着くと、まずは無機質なガラス扉をくぐる。中はいつ来ても同じで、古びた紙の匂いがする。昼だと言うのに薄暗く感じるチープな蛍光灯に照らされ、「振り込め詐欺にご注意を!」と書かれた派手なチラシが壁に貼られているのが視界の端にチラリと入った。
受付にいる女性警官に声をかけ、顔馴染みの刑事を呼んでもらう。俺の名前を伝えると、一瞬『またコイツらか』といった顔をされた気がするが、直ぐに顔を無表情に戻し、「少しこちらでお待ちください」とだけ答えた。
待つしかできないので、俺はドサっと待ち合いのベンチに腰を下ろす。汗がまとわりつきそうな合皮のソレに、先に座っていた依頼人サンは両手をキツく握りしめ、視線を床に落としたまま動かない。流石になんて声をかければいいのかわからず、制服警官たちが忙しなく行き交う空間の中で、俺たちのいる空間だけが痛いほどに静かに感じた。
しばらくすると、スーツ姿の――いつも事件で世話になったり世話をしたりな――美人な刑事が足早にやってきた。あいかわらず颯爽としていて、周囲の制服組よりよほど頼もしい。俺の顔と、その横で蒼白になっている依頼人を見るなり、すぐに「こちらへ」と個室へ案内してくれた。
通された個室は、4畳半ほどの簡素な会議室だった。壁は灰色がかった白、パイプ机と椅子が並べられたそこは妙に乾いた空気で、古めかしい音を立てながら懸命にエアコンが稼働していた。
俺たちが椅子に座ったことを確認すると、刑事が扉を閉めて、向かいに腰を下ろす。
「さて……じゃあ、詳しく話してもらえるかな?」
胸ポケットからメモ帳を取り出し、水色のボールペンをかちりと鳴らした。しかし、唇が紫になっている依頼人サンはうまく話せそうにない。仕方がないので、俺が昨日起きた一連の出来事を刑事へ伝えていく。彼女から依頼を受けて調査に入ったこと、夜に侵入者があったこと、その姿を捉えたビデオがあったがデータが消えてしまったこと。
刑事は黙って俺の話を聞き、途中で何度か眉を顰める。
「その侵入者の特徴はわかった?」
「いやァ……先に着いたのはレムナンだったし、それも物音で裏口から逃げていく姿を見かけただけっぽいから……体格的には成人男性だとは思うけどよ」
ラキオのカメラで一度だけみた映像に映る姿は、それなりに長身の男性のように見えた。しかし、なにぶん夜間カメラで画素もざらついていたので自信はない。
「ふむ……」
刑事が依頼人サンに視線を移すと、彼女はびくりと肩を揺らした。それに気付いたのか、優しい声色で刑事が続ける。
「では坂東さんでしたね、昨日の今日でまだ落ち着くのは難しいとは思う。けれど、貴方の話も聞かせてもらえないかな?」
貴方の力になりたいんだ、と言う刑事の真摯な言葉に依頼人さんは黙って首をコクリと縦に動かした。
「ありがとう。必ず貴方に不利のないように動くから安心してほしい。それで、申し訳ないんだけど犯人に心当たりはないかな?」
あまりにも直球な質問に、俺の方がドキリとしてしまう。
「心当たり……ですか。いえ、特には……」
一方の彼女は、少し思案しながら小さい声で答えていく。フォローするように、刑事が続ける。
「もちろん、貴方が何か犯人にしたとかそういうことを考えているわけではないよ。ただ、些細なきっかけでも恨みを持つ人間はいるから……」
「ありません」
食い気味に答えた依頼人サンに、刑事も俺も珍しく面食らう。緊張しすぎてややハイになっているようにも見える姿は、そのままやや裏返った声で言葉を紡いだ。
「わ、私のことを。嫌いになる、ような人は、いないと思います」
「……わかった。では、物証から犯人を探るのが一番早いか……」
刑事は深く息を吐き、取っていたメモに視線を落とした。
「なるべく早く動いてみるよ。ただ、所長の撮ったビデオという物証があるのが一番早いんだけどね」
顎に手を当て、難しい顔をしながら刑事が言う。
「ビデオな……霊障?か、なんかでデータが全ておじゃんになっちまったんだと」
朝見たげっそりした顔つきのレムナンを思い出しながら、俺は答える。機械のこともさっぱりだが、アレは復元に骨が折れそうな顔だった。
「またオカルト絡み?」
やや苦笑まじりの言葉に、俺は肩をすくめて肯定の意思を示す。
「そういえば、盗聴器が仕掛けられているのかもしれないんだろう?それはどうしたんだ?」
「あっ……」
完全に頭から抜けていた。
俺が思わず額を抑えていると、刑事の視線が鋭くなる。
「それがあれば、ビデオの映像がなくても証拠になる。すぐに回収したほうがいい」
その通りだ。
急いでそれを回収しに戻りたいが、あの家にまた依頼人を戻すのも気が引ける。何より鍵はラキオたちが持っていってしまった。どうしたものかと考えていると、俺の携帯がうなりを上げて震え出した。
慌ててポケットに突っ込んでいたスマホを取り出すと、そこには光り輝くディスプレイに短く文字が映し出されていた。
『すぐに戻ってきなよ。そこにいる刑事も可能なら同伴してもらってくれ』
それは、ラキオからの連絡だった。