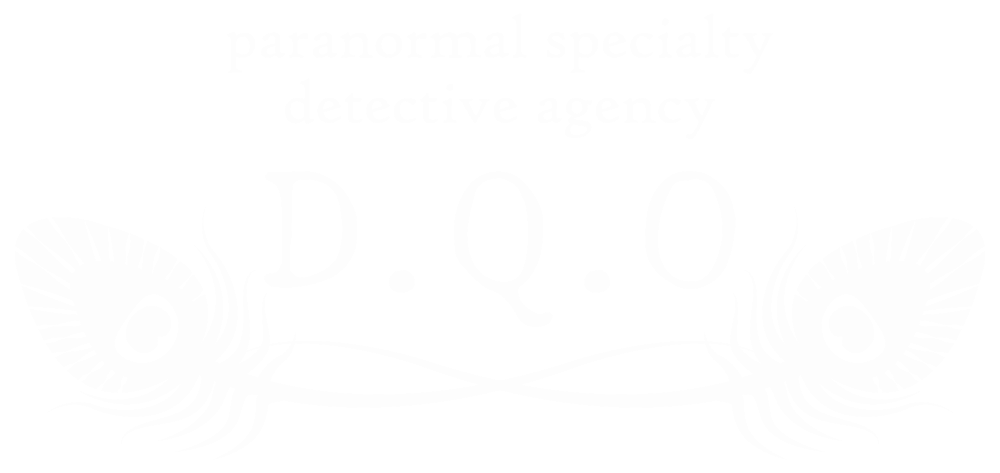三
「違うって、どういう意味だ?」
俺はレムナンに尋ねる。ラキオもイマイチ釈然としないようで、怪訝な顔をしていた。
「家の中にいるのは……理由はわからないですけど、悪意はないんです。かといって守護霊とか、座敷童とか、そういう……ポジティブなイメージで語られるようなものでもない、と思います。本当にただ、ここに縛られていて、逃げられない。ここにいざるを得ない、という感じです」
「……で、おじいさんでもおばあさんでもない。正体不明のナニか?」
「はい。でも裏庭から感じるのはもっと、直接的な……嫌な感じです。家の中より明確に、恨みだとかそういった感情が渦巻いている……ような」
上手くは言えないんですけど……と目を伏せてぼそぼそ口を動かす。
「かといって、この裏庭にある気配は動くとか、逃げ惑うとかでもないです。家の中には入ってこられないというか……うん、恨みはあるけど力もない、そんなイメージでした」
「つまり、だ。君は今日一日の調査の中で、この家に存在する超常現象には二種類ありそうだ、と感じとっていたわけだ。機械類には反応もされないような微弱なものの差を感じ取れるんだから、なかなか優秀な測定器だよね。もっとも数値化できない直感とやらによるものだから、僕の研究のデータとしては全く使えないんだけどさ」
なにが嬉しいのかニコニコと話すラキオに対して、レムナンの顔は淀んで暗いままだ。
「で、そこまでわかってんのに何で依頼者サンの前で言ってやらなかったんだ?」
「……この家にいる程度の霊なら、普通の人は変な感じを察することすらない、と思います。物を動かしたり、何かしたりも出来ませんし、それに、」
「待って」
突如鋭くラキオが声を上げて制止したのは、レムナンが続けようとした瞬間だった。
そのまま煌びやかなネイルが施された指が、ある一点を指差す。
――裏庭。
裏庭のモニターに、先程まではいなかったはずの、“何か”がいる。
モニターを見た瞬間、弾かれたようにレムナンが部屋を飛び出す。ビビって固まっていた俺も、ワンテンポ遅れてその後ろを慌てて追いかける。
けたたましくバタバタと走る足音に呼応する、廊下のギィギィと軋む音。
昼間は気にならなかったじめっとしたカビ臭い匂い。
なにもかも不快で気味が悪い。この家は、こんなだったか?
いやに寒々しい台所の勝手口を抜け、裏庭へ飛び出すと、一足先に到着していたはずのレムナンが切り株の近くで苦しげに肩で息をしているのが目に入る。サッと血の気が引き、慌てて肩を掴んだ。
「ハァ……ハァ……、沙明さん……、ゲホッ、すみません、ちょっと急に走ったので……」
なにか危害を加えられたわけではなさそうだ。氷水を浴びせられたかのように冷たくなっていた指先に、少しずつ血が巡る。
「お前さぁ……1人で行くなよ!なんかあったらどうすんだ!?」
「す、すみませ、ん……慌ててて、取り押さえないとって……」
柄にもなくデカい声で怒鳴ってしまった俺に、ゼェハァ言いながらも珍しくレムナンは素直に謝った。どうやら先走ってしまった自覚はあったらしい。これ以上責めるわけにもいかず、代わりに周りを見回したが、俺にはなにも見えそうにはなかった。
「……人影は?」
「僕が走ってくる音に、びっくりしたんでしょうか。そこから、出て行っちゃいました」
掠れた声でそういって、指差すのは倉庫の横の古びた扉だ。
そういえば依頼人が『閉めたはずの裏庭の扉が開いていることがあった』と話していたことを思い出す。
レムナンにはそこで休むよう伝え、恐る恐るアルミでできた扉のドアノブにそっと触れる。
すると扉は、まるで外へ誘うかのようにスルリと開き、隙間から流れ込む生温い夜風がゾワリと俺の頬を撫ぜた。
背筋がざわつく嫌な感じを覚えつつ、はやる鼓動をつとめて抑えてスマホのライトを外へ回していく。
しかし、その先はなんてことない――一方通行の道だった。来るときにも見た、住宅街のありふれた風景。街灯に点々と照らされたその道は、スマホの弱々しい光なんてなくても十二分に明るい。
ひとまず不審な人影とやらに、直接対峙しなくて済んだことに俺はあらためて安堵した。
こんな仕事をやってはいるが、俺のモットーは『安全第一』だ。出来ることなら、怪しい奴とお見合いなんてのはしたくない。
「……っはぁ〜!緊張した!マジでびびった!もう、マジで嫌!ほんと嫌!!」
気休めにもならないだろうが、とりあえずデカい声を出しながら扉を閉め、内側の鍵を後ろ手にすぐさま回す。
そして切り株の横に座っているレムナンの元へ戻ると、同じタイミングで所長サマもようやくご到着のようだった。
「まったく勢いがあるのはいいけれど、もう少し冷静になって欲しいものだよね」
悠然と歩いてくるラキオの足元はしっかり靴で守られており、ご丁寧に自分だけは靴を履いて裏庭へ出てきたようだった。
そういえば、俺とレムナンは裸足のままだったと今更気付く。途端、湿り気のある土が足裏にへばりついていることがたまらなく不愉快に感じた。うへぇ、とこぼしながら、軽く足裏をパンパンとはらう。
「ここを見なよ」
そんな俺にはお構いなしに、ラキオが自分のスマホの画面を見せてきた。
モニター類とリアルタイムで接続されているので、片足をあげて妙なポーズをとっている俺の姿が目に入る。
「カメラ映像じゃなくて、こっち」
「……サーモグラフィー?」
「そう。君たちが勇猛にも飛び出して行った後、僕はきちんと数値を確認していたンだ。当然だよね?そうすると、なかなか面白いものが見られてね」
そういうと、裏庭の映像を少し遡る。俺らの形をしたぼんやりとした黄緑がかった光と入れ替わるようにして現れたのは、同じような色をした人影だった。
「ポルターガイストなどで移動した物体が熱を持つと言うことはある。しかし、この温度や動きを見ると、この人影自体が熱を持っているじゃあないか。おかしいよね?なんでかわかるかな?沙明」
「……霊障が起こると、その付近の気温は下がる」
俺は何度目かになるかわからないため息をつきながら、そのラキオクイズに答える。
「正解!つまりね、君たちが追いかけた人影はなんてことない、ただの人間だったってワケ!」
「いや、それはそれで怖いことには間違いないだろ……」
あっけらかんとのたまうラキオに、力なくツッコんだ。