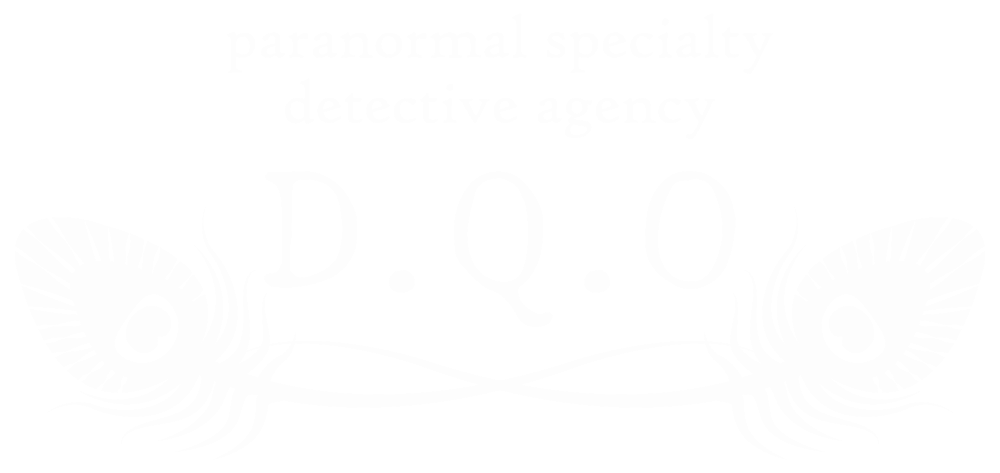一
後日、約束を取り付けられた日。
彼らが私の家のインターホンを鳴らしたのは、朝の10時ピッタリというタイミングだった。
社用車にしては随分古めかしく洒落たクラシックカーからは、先日お会いした小柄な少年と、オセロみたいに真反対の見た目をした二人が降りてくる。不思議な現象の調査、というからてっきりお坊さんとか、巫女さんとか、いかにもえらい感じのお爺さんとかが呼ばれるのかと思ったけれど、先日見かけた三人だけらしい。前も思ったが、なんだか現実離れした光景だ。一体どういう関係性なのだろう……。私の思考が明後日の方向に働きかけたところ、一刻も惜しいといわんばかりに、所長さんが口を開く。
「伝えたとおり、調査の拠点として一部屋使わせてもらうよ。空き部屋は準備しているよね」
「あっ、はい!こちらに」
現実に引き戻された私は、慌てて彼らを畳敷きの六畳ほどの部屋へ案内する。一応、掃除はしておいたが……如何せん古い家なので、私が気付けない匂いがあったらどうしよう。お客様自体呼ぶこともないので、急に不安になってなんだかソワソワしてしまう。しかし、そんな私の落ち着きのなさは微塵も気にせず、彼は案内された部屋をぐるりと見回して、テキパキ指示を出し始めた。
「では、早速調査に取り掛からせてもらう。レムナン、沙明、機材の準備を」
鶴の一声で白髪の子と黒髪の男性が、働きアリのようにせっせせっせと大きな荷物を車から次々と運び出してくる。一体何を持ってきたのかと、部屋に運び込まれた荷物をそっと覗き込むと、大きなビデオカメラだったり、沢山のモニターや集音マイクのようなものだったり、サーモグラフィーセンサーなんてものがぎっしり詰められていた。重そうなそれらを抱えた二人が、ヒィヒィ言いながら何往復もしているので、何か手伝いましょうかと声をかけたが「……いりません。これ、高価ですし……」とキッパリ断られてしまった。
しばらくして、空き部屋はすっかり特撮番組の秘密基地かなにかといった形相に様変わりしていた。
畳の上にはカーペット、その上に簡易なパイプ棚が置かれ、中にモニターとパソコンが何台もズラリと並べられている。カメラなどはまだ雑然と床に置かれたままで、あらかじめお渡ししていた見取り図と睨めっこしてあーでもない、こーでもないと白髪と黒髪の二人が軽く汗を拭きながら相談している。
完全に手持ち無沙汰の私は、指示を出した後は我関せずといった顔で椅子に座り、涼しげな顔で本を読んでいる所長さんへ話を振ってみる。
「あのー、お祓いとかはしないんですか?」
「必要であれば。その時はまた知り合いにこちらから依頼する。だから依頼者の君がそんなことまで考えなくていい」
とピシャリ。
はい、そうですか……。
すでに今日だけで、二度も冷たくあしらわれてしまっている。……私の話し方が悪いのだろうか。1人反省会をしていると、黒髪の軽薄そうな男性が、首をポリポリと掻きながら話しかけてきた。
「あー依頼者のー、坂東?さんっしたっけ?これから、この家で起きている事が超常現象かどうかってのを調査してきますわ。とりあえず、データ取らせてもらいたいんで、各部屋にカメラとかを設置したいんだけど、オーケー?」
薄ら笑いを浮かべた顔付きは最初と変わらないはずなのに、もはや気さくな態度というだけで少し安心する。
「ええ、もちろん。構いません、えっと、どこに……?」
「だってよ、どこに置いてく?」
「依頼人のいう、おかしな事が起きた部屋全てに。廊下や玄関などにも必要そうであれば置かせてもらおうか。そこで異常なデータが取れれば、さらにそこを重点的に。……数日もあれば、この家で起きていることが科学的に証明できるものか否か判断できるだろうね」
「では、裏庭や台所、シャワー……おばあちゃんの部屋、あたりでしょうか。一階からご案内させていただきますね」
なんとなく家全体的に変な感じはするが、具体的に何かがあった気がするのはそのあたりだ。私は黒髪の男性――沙明さんと、白髪の青年――レムナンさんを先導し、問題の部屋へ向かうことにした。
「えっと、まずはここです。おばあちゃんの部屋として使っていました。一月ほど前に、デイの時間が近くになっても起きてこないので……確認しに行ったら布団の中で既に……。あっ、掃除はしてあります!」
一階の玄関入ってすぐ左に位置しているその部屋は、おばあちゃんの使っていたお香のような甘い香りが畳やふすまに染みついており、独特の匂いがする。なにより、不審な点はなかったとはいえ、人が亡くなった部屋だ。なんとなくお客様を通すのは申し訳ない気持ちになる。
「そんな気にしなくても大丈夫ッスよ。つーかお祖母さんが亡くなってすぐなのに、色々あってマジ大変でしたね。……で、この部屋では、何が?」
そう言いながら、手を合わせてから沙明さんは部屋へ入ってくる。
「えっと、たまに声がする気がする……というか、それくらいですね、この部屋は。換気とか、掃除のときくらいしかあまり入らないもので……」
私が起こった事を思い出しながら沙明さんと話している間も、レムナンさんは眉間にシワを寄せたまま一言も口を開かない。手に持ったメジャーで何かを測定しては、案内された部屋の寸法を間取りと見比べたり、書き込んだりしているようだ。話をあらかた聞き終えた沙明さんが、その図面を覗き込み、話しかける。
「レムナン、どーよ?」
「……うーん、正直、まだなにも……という、感じでしょうか」
「あっそ、じゃあ所長サマの言うとおりに機材を設置して……っと。スンマセン、電源お借りしまーす」
テンポよくやらねーと遅いってドヤされるからさ〜と沙明さんがボヤき、それを小さな声で嗜めるレムナンさん。思わず笑いそうになるが、レムナンさんにジトっとした目を向けられた気がして、あわてて私は表情を正す。
「じゃ、次は……台所っすかね。間取りで見た感じ」
そんな一連のやり取りを気付いているのかいないのか、沙明さんはあっけらかんと話を進めていった。
促されるようにおばあちゃんの部屋から出ると、そのままキィキィと軋む廊下を左の突き当たりまで進む。
木製のビーズで出来たすだれのれんをくぐると、そこはこじんまりとした台所だ。生前はおばあちゃんが丁寧に掃除をしていたから、古びてはいるものの綺麗だと思う。使いやすいようにお玉や鍋蓋が掛けられる自作のフックがコンロ沿いの壁に付けられていたり、アクリル毛糸のタワシがシンクにぶら下がっていたり、ここへ来るだけでおばあちゃんの生きていた証を感じられる気がするので、私はここが好きだ。私の気持ちを汲むかのように、沙明さんが感心しながらに呟く。
「ホーン、レトロな感じだけど、お手入れはしーっかりやってらっしゃるんすねェ」
「はい、おばあちゃんが大事にしていたので……最近はすっかり料理もサボってしまってますが、柔らかくお粥を炊いたり、刻んだ菜っぱの煮付けを作ったり、よくしていたんです」
「……お祖母さん思いなんすね」
「いえ、そんな……無職になった私に優しくしてくれたのは、おばあちゃんだけでしたし。その分くらい、大事にしたかっただけです……返し切れたとは、思えませんが……」
「そんなことないっしょ。孫が一緒に暮らしてくれて、最期までそばに居てくれたんならそれだけでも嬉しかったんじゃねーかと俺ァ思いますし」
ま、会ったことないんでわかんないすけど!とわざと軽く笑う沙明さん。お世辞かもしれないが、その優しい言葉に私は思わず表情が綻んでしまう。
「で、そんな思い出深いキッチンでは何があったんすかね」
「うーん、ここでも同じ、でしょうか……声がする、というか。ガスでお米を炊いている筈なのに、時折急に寒くなった気がするとか……」
「お祖母さんの部屋と同じ感じかァ〜」
念の為、何か不審なものが無いかとシンク下の扉や食器棚もあらためる。しかし、そこには使い慣れた菜切包丁や肉切り包丁がピカピカに磨かれて置かれていたり、二人暮らしではあまり使わなかった寸胴鍋が残っていたり、蒸籠やタジン鍋などの憧れて買ったはいいが使いこなせなかったものたちがこまごまと出てくるばかりで、特に変わったものが出てくるわけでもない。
そんな調子で残る浴室や、裏庭なども順番に細かく見て回った。だが、機材をセッティングする間、一人の時に感じていた寒気や声を感じることは遂に一度もなく、レムナンさんと沙明さんも、各々なにかを調べては怪訝そうに首を傾げるばかりだった。
一通り機材を設置し終える頃には、すっかりお昼を過ぎてしまっていた。
後半は、私もコードの配線くらいは手伝わせてもらえるようになり、少し打ち解けられたような、気がする。終始、沙明さんが私とレムナンさんの間に入って、あーだこーだと喋ってくれていたおかげもあるだろう。
軽く汗ばんだ額を拭いながら最初の部屋へ戻る。襖の開く音でこちらに気付いたらしい所長さんが、分厚いファイルから目をあげた。
「随分と時間がかかっていたようだけれど、僕が思っていたより広大なお屋敷だったのかな?」
「そーそー所長サマは、一回りするだけで疲れちまいそーなベリーベリー広いお屋敷だったぜ?隠し部屋に、踏むと槍が降ってくる床だろ……」
開口一番の皮肉を全く気にしない様子で、沙明さんが軽口で返す。そのやりとりを見てわかりやすくため息をつきながら、レムナンさんはなにかを書き込んでいた間取りをラキオさんへ手渡していた。それを軽く一瞥すると、
「フン、まあ仕事はきちんとやってきたみたいだからね。及第点というところか……早速、計器類を確認していこう」
ラキオさんの座る椅子の前に設置されたモニター群には、先ほど設置してきたカメラからの映像がリアルタイムで流れている。その横に沢山の数字や、よくわからない波形のようなものも映されており、勝手知ったる家であるはずなのに、モニター越しに映るそれらは、まるで別の世界のようだ。
倍速で同時にそれらをラキオさんが確認していったが、特に変わったものもなにも映り込んではいないようだった。
「一部の部屋の気温がやや低いが、許容範囲内だろう。間取りと実測に大きなブレもないようだし、現時点ではとりたてて異常な点は見当たらない、か」
「……何かがいたとしても、知らない人間がいきなり上がり込んできたので、一時的に鳴りを潜めている可能性もあると、おもいます」
「フーン……じゃあ君は、何か感じたワケ?」
そう話を振られると、レムナンさんはラキオさんと私の顔をしばらく見比べた後、また軽くため息をつく
「……明確に何かが視えた、というわけでは、ありません。ただ……何かが澱んでいる、そんな気はした……くらいでしょうか」
特にこの部屋とこの辺りですかね、とレムナンさんが指差すのは台所と裏庭。
私には何もみえないが、そこに本当に、なにかが……。さっき一緒に機材を置きにいった時、私は何も感じることができなかったのに。急に背筋がゾワゾワとして、キョロキョロと落ち着きなく周りを見回してしまう。
しかし、そんな私の重い気分とは裏腹に呑気な声が耳に届いた。
「アー、でも昼にそーゆーのって大体動きにくいだろうし、今のうちに軽く昼飯でも食いに行っとかね?依頼人サンにもその方がいいっしょ」
と沙明さんがなんてことないように言い、意外なことに所長さんもそれに賛同する。
これがプロの余裕というやつなのだろうか。
「……それもそうだね。君たちにはまだまだ肉体労働に勤しんでもらう必要がある。一度、補給に行くのも悪くない。どうせ、夜は寝ずの番なンだ、ついでにテイクアウトでも頼んでくるといいよ」
と、不用心に財布を沙明さんの方へ放り投げる。アザーッスと軽く礼を言う沙明さんの声を上書きするように、聞いたことのない音量でレムナンさんが声を上げた。
「えっ、この家に、一人で残るんですか……?」
「そうだけど?」
「駄目です。まだ、何も起きてませんけど、何かがあったとき、貴方一人じゃ……」
「そうはいっても監視は続けないといけないだろう。全く……仮にも依頼で僕たちは来ているし、危険があれば逃げるくらいの判断を僕ができないとでも?大体、ぼんやり何かいる気がするって程度で今は沈静化してるって君自身が言ったンじゃないか」
「じゃあ、僕が……」
「いや、それだと僕が残るのとそんなに変わらないよね」
「全然違います!」
今度はラキオさんとレムナンさんがやいのやいの、喧々囂々と言い争いを始めてしまった。さっきは沙明さんと言い合いをしていたし、本当にこの3人は大丈夫なのだろうか。機材をセットする中で、ちょっとだけ芽生えていた信頼の芽が急激に元気をなくしていく。我関せずといった様子でしばらく眺めていた沙明さんも、やがて呆れたように口を挟む。
「お相手さんはナニか、落ち着いてんだろ?こういうのは敢えて押して駄目ならンーフーンーフー……って感じで、逆に誘ってやるのもいいんじゃね?」
暗に、『もういいから全員でとっとと出かけようぜ』という気持ちをビシバシと滲ませる声色だった。だが、意外にもその沙明さんの物言いには納得する節があったのだろうか。
「……1時間以内には僕は帰らせてもらうからね」
と、所長さんは立ち上がり、私たちの誰よりも先に玄関へ向かっていってしまった。
彼らと共にやってきたのは、歩いて程近くのチェーンのファミレスだ。
ランチどきを少し過ぎたせいもあり、店内の客入りはまばらであり、勉強している学生やドリンクバーのカップをたくさん並べておしゃべりに興じている人たちなどが穏やかに過ごしている。先ほどまでの非日常な空間から一転した、よくある風景。それを眺めていると、お肉の焦げる匂いがダイレクトに胃袋へアタックしてくるのを感じた。
「えーっと、坂東さん?でしたっけ?なんか食います?ステーキフェアとかやってますけど」
そう言いながら沙明さんがメニューをこちらへ手渡してくれる。残る二人は、私のことを気にも介さないようにさっさと注文の用紙を記入して、間違い探しをしていた。
「あ、大丈夫です。お肉、苦手で……エビのサラダとパンがいいです。あとアキと呼んでもらえれば……嬉しいです。勿論良ければ、ですけど」
作り慣れない笑みを彼へ向けると、そっすか、んじゃそれでと軽く言いながら、代わりにオーダーボタンを押してくれた。