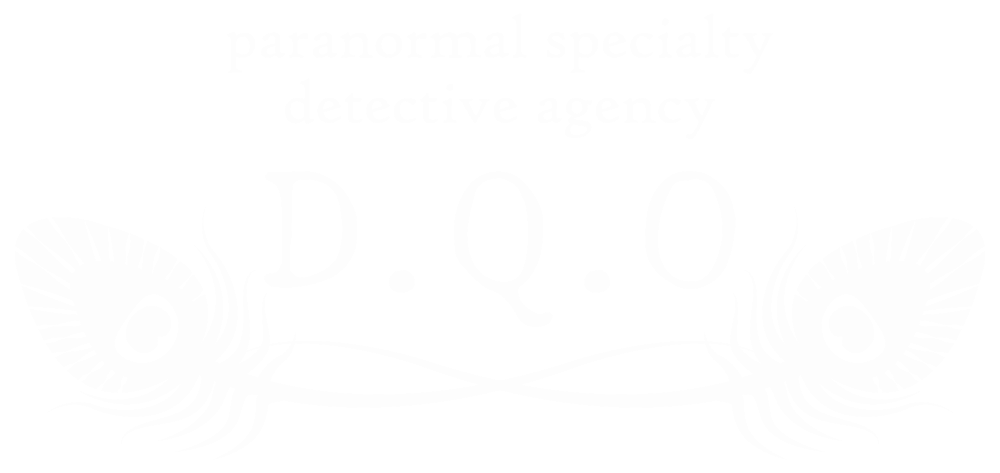エピローグ
「随分、疲れる事件でしたね」
少女のような微笑みを浮かべたままの彼女が、警察官に連行されるのを見送ってから、僕たちは事務所へ帰ってきた。
沙明さんは「とんでもねえ美人だったのになァ」とか、「こう……パキッとした顔立ちに、陰のある雰囲気がさぁ……」とか、いつもの調子でふざけている。しかし、その声にはどこか力がなかった。あの依頼人と、僕たちの中で一番親しく言葉を交わしてしまったのは、間違いなく彼だったのだから。
僕は片付けの手を止めずに、そっとその横顔を盗み見る。けれど、いつも通りヘラヘラと笑う彼の真意はまるで掴めなかった。深く息を吐いて、手元のファイルをどうするか思案する。 ラキオさんはといえば、パソコンで何やら打ち込んでいる様子だ。キーボードを軽やかに叩く音が、事務所の中に規則正しく響く。そして不意にその口を開いた。
「坂東アキ――ああ、いなくなってしまった“本物”の方ね」
そのあまりにも不謹慎な言い様に、思わず僕は手に持っていたファイルを滑り落としそうになる。
「ちょっと、ラキオさん……」
「ちょうどいい。君の持っているそれ……3ページ目だったかな。本物からの依頼内容が記載されていたはずだよ。興味があったら読んでみるといいンじゃない?」
促され、恐る恐るページを沙明さんと共に捲る。
『坂東アキ』――。
表紙に印字されたその名を見た瞬間、心臓がヒヤリとした。元々これは、「未処理依頼類(所定期間管理後破棄)」――メールや電話で依頼を受けながらも、調査に至らなかった案件ばかりをまとめた膨大な資料のうちの一つだ。
調査に至らない理由のほとんどは「ラキオさんの興味を惹かなかった」から。一応、ごく稀にだが依頼人からの一方的なキャンセルや、アポ直前で依頼人が音信不通になったケースも混じっている。
これらの中にもしかすると、「本物が紛れているかもしれない」と、ラキオさんに無理を言ってファイリングしはじめたのは僕が働き始めてからのことだ。ラキオさんは、本物の可能性なんて低いし、そもそも書面に残しておかずとも記憶しておけるから不要なのに、とこれの存在に酷く懐疑的ではあったけれど。実際、ほとんど資料室の肥やしになっているだけであったし――。
しかし、その資料がようやく日の目を浴びた。
最初に坂東アキが事務所に訪れた際、その名前を覚えていたラキオさんがその肥やしの中から該当する資料を沙明さんに探させていたらしい。あの時、沙明さんが資料室からラキオさんに手渡していた資料がどうやらこれのようだった。
そこに記載されていた相談内容は
『最近知り合いにストーカーまがいのことをされている。気味が悪いから調査してほしい』ということだった。
「これは確かに、僕たちに依頼されても困ります。ね……」
「だよなぁ。でも、このストーカーってさ……」
隣で一緒に資料を覗き込んでいた沙明さんが何かに気付いたかのように言いかけ、唇を噛んで黙り込んだ。
キーボードを打鍵する音だけが、再び事務所に戻ってくる。
ラキオさんは視線をモニターから外さずに言った。
「この依頼が持ちかけられた時期から考えると、間違いなくそのストーカーは今回の依頼人だろうね。そして、本物の坂東アキは――その直後に姿を消した。……理由は不明だけどね。そして、彼女そっくりに整形した女が、“アキ”を名乗り、祖母の元へ身を寄せて生き始めた。仕事も辞め、婚約者も切り捨てて。本物のエミュレートとは程遠いけれど……まぁ、誰も気付かない程度には上手くやっていたンだろう」
一気に捲し立てると、ラキオさんは椅子の背にもたれて目を閉じた。
「……あれも一種の愛なんかね。神様〜とか、流石にテリブルすぎてあんな美人でもお断りだけどさ」
と沙明さんが冗談めかしたように、肩をすくめる。
「僕でさえ、あれが愛ではないことくらい分かるよ。ただの執着でしかない。交配本能以下の、悍ましい征服欲だと思うね」
ラキオさんは鼻で笑い、淡々と切り捨てた。小気味のいい会話が繰り広げられる中で、無意識に僕の口から言葉が溢れる。
「彼女、捕まるんでしょうか……」
「本人の言うとおり、坂東アキが受け取るべきだった遺産を不当に受けとっているからね。詐欺などで立件できるかもしれない。……けれど、本物の坂東アキがどうなったかが証明できない以上、これ以上の追求は難しいンじゃないかな。死体でも出てくれば話は変わるかもしれないけどね」
――死体が出てくれば。
その言葉が頭の中で何度も反響する。
あの家には、坂東アキの霊が“いる”。依頼人と同じ顔を苦悶に歪めて、時折影法師のようにゆらめいていた彼女。彼女は、助けを求めていた。
『ここから出して』そう訴えているのだと、ハッキリ理解したのは、依頼人があの家に不在になった瞬間だった。
元婚約者が来た時に、ポルターガイストが起こったのもそうなのだろう。
彼女は、依頼人に怯えながらも誰かに助けを求めようとしていたのだ。
あの人はもう、間違いなくこの世にはいない存在だ。
犯人は言うまでもないだろう。だが、証拠がない。
依頼人は、車を持っていなかった。なら人間一人の遺体をどう隠蔽した?庭へ埋めた?切り刻んで捨てた?
……どれもしっくりこない。
――どうしても“坂東アキ”を遺したかった。一緒にいたかった。
そうウットリと語るあの女の顔が忘れられない。あれだけのことを平然と犯して「愛」だと宣う女。
そんな人間が、愛する神様の亡骸を無碍に扱うだろうか……。
ぞくり、と背中に冷たいものが伝う。
これ以上考えても仕方がない。
考えれば考えるほど、まともな思考が深い泥に引きずり込まれていくだけだ。
そう自分に言い聞かせて、ファイルを閉じた。そして乱雑に資料庫の中へ放り込む。
「よし、打ち上げ行こうぜ〜。焼き肉とかさ」
呑気に言う沙明さんの声が、少しだけ救いのように響いた。