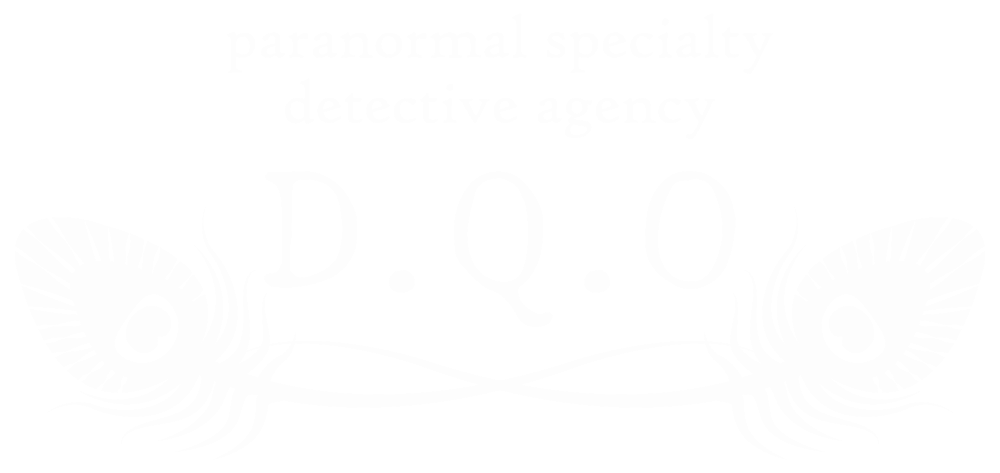「ちょっと君たち、仮にも社用車なンだから使った後はきちんと綺麗にしておいてくれないか」
いやというほど眩しい朝日に包まれながら僕と沙明さんが事務所へ戻ると、ラキオさんからいきなり棘のある言葉が飛んできたので面食らう。
――今日、というか昨日から僕たちはラキオさんの命令でとある祠へ行っていた。
そこは伝承にもほぼ残っていない土祖神を祀っているとかなんだかで、結構な山の中にある場所。
とある大学生のオカルトサークルが制作したZINEに小さく掲載されただけのそれは、他に目ぼしい資料もなかったに関わらず、我らが所長様の関心をえらく引いたらしい。信憑性なんてあって無いに等しい気もしたが、そんなものを一介の学生がわざわざ記事にすること自体が奇妙なので面白い、とのことだった。まぁバイト代が出るなら行くけどさ〜とぶつくさ言う沙明さんに倣い、僕も素直に遠征を引き受けた。
眠い目を擦りながら早朝に出発した甲斐があり、昼前にはなんとか祠へ到着できた。
頼まれていた写真もバッチリ、地盤の緩みや水脈がないことなどもきちんと計測したので上々だろう。沙明さんが聞き込みもしたが、地元の人すらそこに祠があることを知らなかったようだ。これ以上は僕たちには何もわからないと、夕方には調査を終える。
予定通りなら日付が変わる前には事務所へ帰れるはず、だったのだが。
運悪くも帰りの高速道路は事故渋滞。数km以上がカーナビ上で真っ赤に染まっており、ノロノロとしか動かない車に僕は無意識で舌打ちをしてしまう。今日中に帰れると弾んでいた淡い期待はしぼみ、調査中に容赦なく日光に照らされていた身体に疲れがドッと押し寄せる。
それは沙明さんも同じだったようだ。遅々として進まない車の流れにフラストレーションを溜めるくらいなら、いっそSAで休憩しようぜとダルそうな口調で提案してくる。幸い明日は日曜日、事務所は休みで僕は予定もない。そのありがたいアイデアに諸手を挙げて賛成することにした。
SAは同じような判断をしたであろう人たちで、深夜だというのにわいわいと混み合っていた。併設の食堂でなんとか空いてるテーブルを見つけると、疲れた身体を滑り込ませ、ほっと一息をつく。
山道を運転してくれた礼〜、と言いながら沙明さんが自販機のコーヒーを2つテーブルに置いた。払いますよ、と言ったが1杯100万円もするレアものだから有り難く頂戴しとけと笑われたので、素直に甘えることにする。
渋滞に巻き込まれるなんて誰の日頃の行いが悪いせいですかとか、いやいや俺のせいではなくねとか、さっきのコーヒー1杯100万円みたいな件、この間見た映画だったらヤクザに酷い目に遭わされてましたよとか、そんなたわいもない会話をしているうちに、疲れとストレスで凝り固まっていた気持ちが少しずつほぐれていく。
そして普段はあまり見ないような深夜のテレビ番組を眺めたり、小腹が空いてきたので大きいカニカマが乗せられているご当地ラーメンを食べたり、雨の音をBGMにして交互に仮眠を取ったりしながら過ごした。夜更けのSAには特有のダラけた空気が流れていたが、学生気分というのだろうか。ほんの少し楽しいとすら思えてきたのは秘密だ。
そんな訳で渋滞が解消してからも、のんびりダラダラしてしまっていたこともあり、帰ってくる頃にはもうすっかり陽が昇ってしまっていた。
夜間は雨が酷かったが、嘘のように今朝は晴れている。ナチュラルにハイになっているテンションのまま、勢いよく事務所の扉を開いて開口一番がさっきのラキオさんのセリフだ。
ほぼ徹夜明けだと言うのにあんまりだ、と思わないこともなかったが、社用車のワゴンにはうっすらとではあるが事務所のロゴマークがあしらわれている。
ラキオさんとの押し問答の末に、ようやく付けさせてもらったロゴだ。そういう経緯もあり、僕は事務所の一員として社用車のワゴンをこっそり可愛がっている。その僕たちの車が汚れているというのは、なんだか可哀想な気がする。昨日だってデコボコ悪路にも負けず懸命に走ってくれた可愛い子だ。日頃からお世話になっているし、ここで一度ピッカピカに綺麗にしてあげよう!と寝不足でやや過活動になった頭は二つ返事で了承した。
最近は日差しが刺すほどにきつく、日中は歩くだけで茹るような気温だが、昨晩の土砂降りのおかげか今朝はまだ涼しい。
……本格的に暑くなる前に済ませてしまおう。
水栓にホースを繋ぎ、自腹で買い揃えた洗車のグッズをあれこれ引っ張り出していった。すると、
「泥汚れっていうか、これ、なんだァ?」
不意に車の前方に立っている沙明さんが怪訝そうな声をあげる。蛇口を締め直し、ホース片手にそちらへ近寄ると、確かに泥汚れとは違う、黒ずんだ汚れがついていた。というよりも、
「……バンパー、凹んでます、ね」
社用車正面、下の方。こんな衝撃を受けるようなことがあれば、運転している時に気づいたはず。
となると、夜間SAに停車している時に誰かにぶつけられたのだろうか。SAから出る時はまだ薄暗かったから、当て逃げされたことに気付かないまま帰ってきてしまったというのはいかにもあり得そうな話だ。
「うぇ〜マジかよ、ラキオに謝んねーとじゃん……」
当て逃げって保険とか効くんだっけ?と心底嫌そうな声をあげながら、おもむろに車の下を覗き込むように沙明さんがしゃがみこみ、手を突っ込み始めた。
「……なにしてるんですか?」
「ン〜?なんか、車の下に白いものが見えた気がしてさ……当て逃げの証拠とか引っ掛かってねーかなって」
腕を肩まで突っ込んで奥の方にある何かを掴もうと懸命に格闘している様子を黙って見ていたが、しばらくして沙明さんは諦めたらしい。ため息をついて立ち上がると、地面につけていた腹あたりの土埃を軽くパンパンと払った。
「こういうのは若者の柔軟性に頼るわ。レムナンの方が目も良いしよ、ちょっと覗いてみてくんね?」
「こんな時だけ年長者ぶって……」
正直少し面倒くさいが、徹夜明けに一緒に洗車してくれている貴重な仲間の頼みを無碍にするわけにもいかず。それに当て逃げだとしたら、犯人を見つけて突き出してやりたいという気持ちもある。湿り気の残るアスファルトに膝をつき、社用車の下を覗き込んだ。
暗くてよく見えないが、確かに白い細いなにかが引っ掛かっているようだ。細い筒の先にさらに細い筒が何本かひっついている奇妙な形。目を凝らしてソレをジッと見定めようとした瞬間、不意にぞくりと指先が凍るような感覚が全身を駆ける。心臓が一瞬止まる感覚と共に、気付いてしまった。
細い筒のようなものは、さまざまな方向に曲がり、その先に、小さな。
車体に懸命にしがみつこうとしたのか。剥がれかけた小さい楕円が目に入る。
――手だ。
咄嗟に自分の手を引っ込めようとした瞬間、後頭部を無遠慮に鷲掴みにされる。そのままザラついた地面に顔を押し付けられ、車の下へ押し込まれる。
なにを、と言いかけた言葉は紡がれることなく消えた。
チラリと見えた紫のリブ袖は、間違いなく沙明さんのものだ。だが、こんな力は、ありえない。今、僕の後ろにいるのは沙明さんじゃない!
咄嗟に空いていた左手でタイヤを掴み、両の足をバタバタさせて後ろの何者かを蹴り上げる。しかし、必死の抵抗も幼子のようにいなされ、尋常ではない力で車の下へ押し込まれ続ける。
突然のことにうあああ、と自然に呻き声が出た。歯がガチガチ鳴りながら、本能的に理解する。
この、車の下の手に、触っては、駄目だ。駄目だ。
力無く引っ掛かっていただけの白い手が、奇妙に折れ曲がった形のまま、ヌメヌメと赤黒く濡れ光り、意思を持つかのように蠢いた。
僕の右手を、掴もうとしている。
締め上げられた様に声が出ない。喉を震わせ、助けを求めるが碌な音にならない。引き摺り込まれないよう、押し込まれないよう、一層激しく足を暴れさせるが、何も意図に介さぬ様にケタケタ笑い続ける後ろの声には届かない。
痛みと恐怖で目が滲む、砂利まみれの口を懸命に開き、音もない空気を叫び続けた。そのか細い音すらを掻き消すように、心底愉しげな笑いがけたたましく響きわたる。
――あの、爪が、僕の、手に触れ、
その時だった
「レムナン?今日は休むように伝えた筈だけど?」
怪訝そうなラキオさんの声が不意に後ろから聞こえた。
瞬間、フッと頭を押さえつけていた力が消え、目前に迫っていた手が口惜しそうに霧散した。
「……ハッ、アァ……ッ、ハッ……」
呼吸を懸命に整える、吸う、吐く、吸う、吐く、声が、出る。
「ら、ラキオさん……すみません、ひっぱって、もらえませんか」
足を無遠慮に引っ張りながら、ラキオさんがいつも通りの喧しいほどのマシンガントークであれこれ話す声が頭上に聞こえる。
生きている。
身体の強張りがその声で少しずつ解けていく、腕に力を込めるとミミズのように車体の下から這いずり出ることに成功した。
身体中湿った砂利まみれ、顔に至っては擦り付けられたせいでところどころ血と汗が滲んで痛い。右手にはホースが絡まっていたし、誰かにそのまま引き摺り回されたかのように蛇行して鬱血していた。
這い出してきた僕の形相を見て、流石に少し驚いた様だったが、すぐに「何があった?」と尋ねてくるあたりがラキオさんらしい。
僕は息も絶え絶えに今しがた起きたことをあるがままに伝える。しかし、話せば話すほどその美しく整えられた眉が怪訝そうに潜められていくばかりだった。
ラキオさん曰く、僕と沙明さんは確かに昨日調査へ行ったが、今朝方には何事もなく帰ってきたらしい。
沙明さんは、報告書はまた今度書くから!まじでレポートがやべえんだったわ!と、締め切りを思い出したとかで早々に大学へ蜻蛉返り。
僕も何を聞いてもぼんやりしていたから、流石に疲れているのだろうと家に帰って休む様に伝えたところ黙って頷いて、事務所から出ていったそうだ。
その後、ラキオさんは僕たちの提出した資料を軽くあらためたらしい。少し遅れて事務所を出ると、帰らせたはずの僕が社用車の下でドタバタ愉快に暴れているのを見つけて思わず声をかけたのだそうだ。
僕の記憶と違いすぎる現実に、言葉を失う。沙明さんに聞いても、おそらくラキオさんと同じことを言うのだろうと言う確信があった。
――いつから?いつからが夢だった?
先ほどの恐怖が脳裏にこびりついている。身体がまたガタガタ震えそうになるので、負けじと太ももをかなり強めに数回叩きつけた。そんな僕の様子をしばらく見ていたラキオさんが、おもむろに口を開く
「……で、例の祠だけど写真が全部消えていたンだよね。遠路遥々調査に行ったのに、何の成果も得られなかったンじゃ、君たちとしても申し訳なくていたたまれないだろうと思ってね」
だからさ、そう言ってニッコリと続ける
「もう一回行ってきてくれない?君の様子を見るに当たりの可能性もありそうだしさ!」
太陽に負けないカラッとしたラキオさんの笑顔に、僕は疲れた笑いで返した。
「絶対に嫌です」